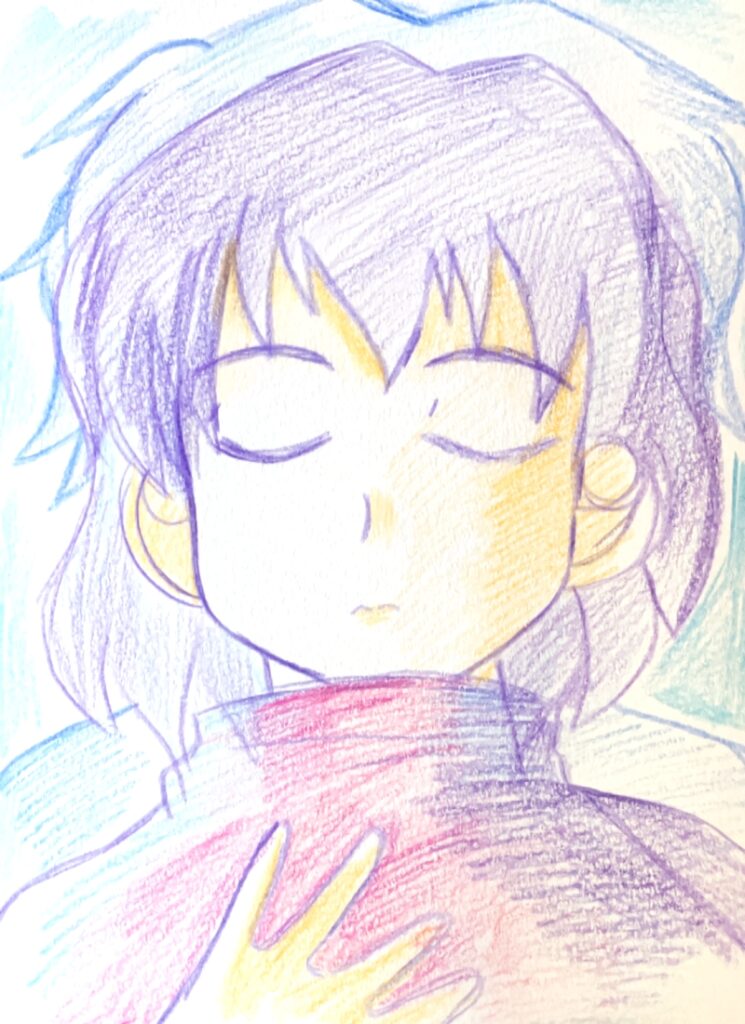〝だが、他人に理解できない辛さを抱えていることは健聴者も変わりないのだ。その辛さの種類がそれぞれ違うだけで。
聞こえるのだから自分より悩みは軽いと決まっているなんて、それこそハンデのある者の驕りでしかなかったのだ。〟
Quoted レインツリーの国/有川浩(新潮文庫 2009.7.1) 174P
落ち着いた状況の今であればこの地の文の意味が理解できるが、前読んだ時にいまいちぴんと来なかったということは自分の障害に対して理解が足りなかったし状況的にもかなり切羽詰まっていたと私は思う。
上記にもある通り、健常である人間が何かしらのハンディキャップを抱えている人間より悩みが軽いとは限らず、ハンディキャップでなくとも何かしら深刻な悩みや心の傷を抱えていることがある。
上記引用部分が指している人物は聴覚障害を抱えており、そこに大きなコンプレックスを抱えている設定である。社会的に安定している主人公(恋人)と喧嘩になった際、主人公に起きた不幸に寄り添えなかったと後に気づくシーンとなる。
上記のポイントは、他者を思いやることにおいて大切なポイントの一つになると思う。自分だけが不幸なわけでもなく、相手や不特定多数の誰かが自分以上の不幸や苦しみを抱えている可能性を考慮する。簡単なようで難しいが、まずは目の前の相手が本当に何も悩んでいないかどうか考えることは重要なんだろうと思う。自分だけが苦しいと思うことは傲慢である。そういうことだ。
上記を要約すると、感情や言葉を抑え込むことで相手を思いやることは十分可能という事だ。(理論上はだが)
相手に対して〝give〟だけではなく〝take〟をするには相手を理解することが必要で、上記も他者理解の一つだと私は考えている。
そういう意味で「レインツリーの国」は障害受容の大きなヒントになる作品だと思っている。