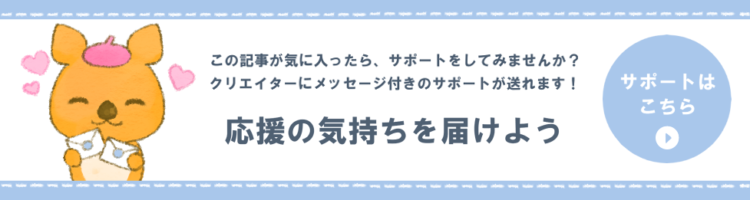「ちょっと、時間くれる?」
そう言いだしたのは優日の方だった。
「いいよ、これから、丁度、期末テストで忙しくなる事だし、1ヶ月後で良いかなぁ?」
「それでいいです。」
「分かった。早く知りたいところだけど、今は我慢をするよ。」
「ありがとう。」
こうして二人の間に長い様な、短い様な時間が流れた。
期末テストが終わった翌週、二人はいつものカフェで会った。
「実は神田さんに話さなきゃいけないことがあります。」
「はい。」
「私は昔、親の愛情に飢えていて、非行に走り『夕日の走り屋』と呼ばれていました。」
「そんな事か。」
「えっ?」
「知ってたよ。だって、俺、隣町の『雷の神田』だもん。」
「えっ?あの?」
「そう、俺、更生してから、大検取って教職免許取ったの。」
「えっ、えっ、えっ?」
「早く俺の正体言えば良かったね。」
「同じ人にはとても見えなかった。」
「そうだよな。当時の俺は尖っていたし・・・。」
「驚いた。」
「渡邊先生なんだ。隣町の荒くれ者なのに、こんな俺とちゃんと話してくれた大人は。」
「へー。」
「偶然だった。緑が丘の不良と喧嘩になって、止めに来た渡邊先生に殴られたんだ。」
「あーやりそう。」
「ハッキリ言って、隣町の先生がなんで、殴るんだと思ったよ。だけどさ、渡邊先生、俺を殴りながら泣いているんだよ。普通、泣けるかな?他人の為に・・・。それから、なんとなく、顔を見ると「元気か?」とか言われて、この人にだったら自分の事を話して良いかなぁと思って。」
「同じだ。うちは母子家庭で離婚するまで、両親は毎日、喧嘩をしていた。家にいる事が嫌で外に出歩いてばかりいたら、悪い仲間に誘われて。そうしたら、渡邊先生に殴られて「両親がどうあれ、自分の人生は自分だけのものだ。自分を大切にしろ。」って熱く語って。「ああ、他人でもこんなに自分のこと心配してくれる人がいるんだなぁ。」と思ったんだ。」
「お互い渡邊先生には頭が上がらないね?」
「そうだね。」
「今度、渡邊先生を訪ねて行っても良い?」
「そうだね。挨拶にでも行くか?」
「挨拶?」
「結婚の挨拶。」
「結婚?」
「嫌?」
「嫌じゃないよ。でも、今のプロポーズ?」
「分かりづらいか?優日さん俺と結婚してください。」
「はい。よろこんでお受けいたします。」
「雨の日の結婚式だけは避けたいなぁ。」
「あはは。良いんじゃない?雨上がりには虹が出るよ。」
「そうか。」
「そうよ。」
二人の世界にはいつも虹が出ているのでしょう。
おわり