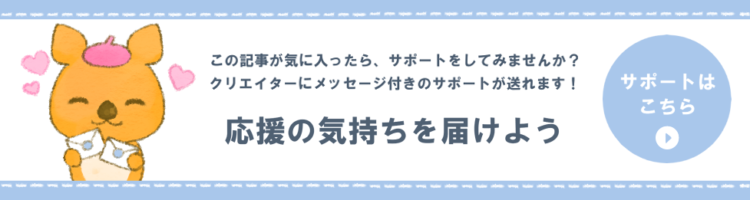「ちょうど、あなたは七夕祭りの花火の日に産まれたのよ。花火を見るどころじゃなかった。」
それが夏花の母親の口癖でした。
その夏花は今年、46歳になりました。。
幼稚園の同僚は20歳代には結婚をして退職していき、夏花は
「夏花さんは仕事に生きる人間だ。」
と周りからレッテルを張られる年をとうに過ぎてしまっていました。
「このまま、親の介護で私の人生は終わりそうだ。」
そんな風に思っていました。
その夏花の趣味は写真でした。
季節の風景の移り変わりを写し撮る中で、自分の人生を重ね合わせていきました。
夏花は毎月、決まって図書館に写真月刊誌を見に行くのが恒例でした。
始めは閲覧するだけでしたが、次第に自分も投稿しようと思いました。
徐々に、佳作から優秀賞を取るまでの実力が付いてきました。
その日は朝から雨が降り、外で写真撮影が無理でした。
いつもの様に、その雑誌を棚から取ろうとしたとき、同じタイミングで手が伸びてきました。
「あっ!すみません。」
「あっ!こちらこそ、すみません。」
「どうぞ。」
「いえいえ、そちらこそ、どうぞ。」
数回、このやり取りが続いた後、夏花は
「一緒に見ませんか?」
「いいのですか?」
「あっ、私の名前は岬 夏花です。」
「夏花先生!?」
「先生?」
「僕です?忘れましたか?」
「もしかして、村木君?」
「はい、村木 祐樹です。」
「祐樹君!わ―懐かしい。何歳になった?」
「今年で24歳に成ります。」
「そうか、私も年取ったものだわ。」
「いえいえ、お若いですよ。今でも幼稚園の先生ですか?」
「同じ幼稚園の主任よ。」
「そうですか、僕は中学校の美術の先生に成りました。」
「そうか。」
「よろしければ。ちょっと、お茶しながら、お話しませんか?」
「いいわよ。祐樹君は私みたいなオバサンとお茶しても大丈夫?」
「大丈夫ですよ。」
二人は「大丈夫」の意味を深く考えずに、お茶をすることになりました。
ある日、夏花が町のコンビニに行った時のことでした。
祐樹は女の子とコンビニにいました。
お互いに気がついた二人は
「こんにちは。」
「こんにちは。」
「そちらは祐樹君の彼女さん?」
「いいえ、同級生ですよ。夏花先生、覚えていませんか?僕を虐めていた きらら ですよ。」
「きらら ちゃん?」
「夏花先生?お久しぶりです。きらら です。これから、同級生たちで飲むことになって、買い出しにきました。」
「そうなのね。」
「彼女だと思いました?」
「ええ、まあ。」
「ありえませんよ。このヘたれと付き合いません!」
「へたれー(;一_一)」
なんとなくほっとする夏花でした。
その気持ちの原因を知ることになったのはそれからすぐのことでした。
「先生。大変!」
「どうしたの?きらら ちゃん。」
「祐樹が・・・。」
「祐樹君がどうしたの?」
「どうしたらいいのかわからないから、夏花先生一緒に来て。」
夏花は何も分からないまま、きらら に連れられて祐樹のアパートにきました。