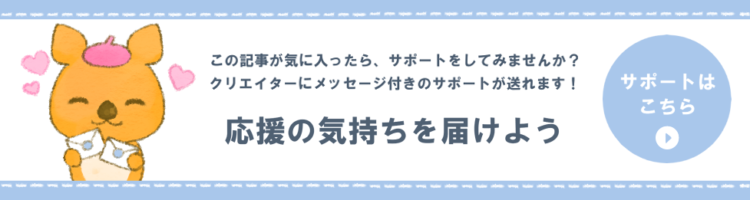「京本君、板垣さんはダメだぞ。」
「なぜですか?」
「婚約までいった奴が、出張に行ったかと思ったらそこで浮気をしていて、破談になったんだ。それから、誰にも心を許さなくなって。」
「そうなんですか。」
難攻不落に思えた紗季を京本は射とめてしまいました。
二人で営業に出かけた仕事終わりのことです。
ふと、ショーウィンドウに飾られたウェディングドレスを見て紗季は思わず泣いてしまったのです。
「どうしたのですか?」
「何でもないです。」
その時、京本は同僚が言っていたことを思い出しました。
「紗季さん、気が済むまで、泣いても良いですよ。なんなら、僕の胸を貸しますよ。」
「そんな事を言う。遠慮しませんよ。」
「良いですよ。僕は紗季さんが好きなんですから。」
「えっ?」
「気付きませんでしたか?」
「ぜんぜん、お陰で涙が出なくなったわ。」
「そうですか?それは良かった。僕の前だけですよ。泣いていいのは。」
「分かってますよ。普段は泣かないのに何で、京本君の前では泣いてしまうのだろう?」
「それは僕に心を許して来たってことじゃないですか?」
「そうか・・・。」
そんな二人には出張期限がありました。
あと、1週間となった期限は瞬く間に終わろうとしていた前の夜でした。
意味も無く街を二人で歩いていたときのことです。
手と手が触れることがありました。
京本は勇気を出して紗季の手を握り締め、紗季にkissをしたのです。
その後、何も言わず二人はそれぞれ帰宅しました。
「あれはなんだったの?」
紗季は何度も問いかけました。
「夢だったのね。」
そう言い聞かせました。
翌日、京本の最後の日、紗季は昨晩のことなど知らない振りをしました。