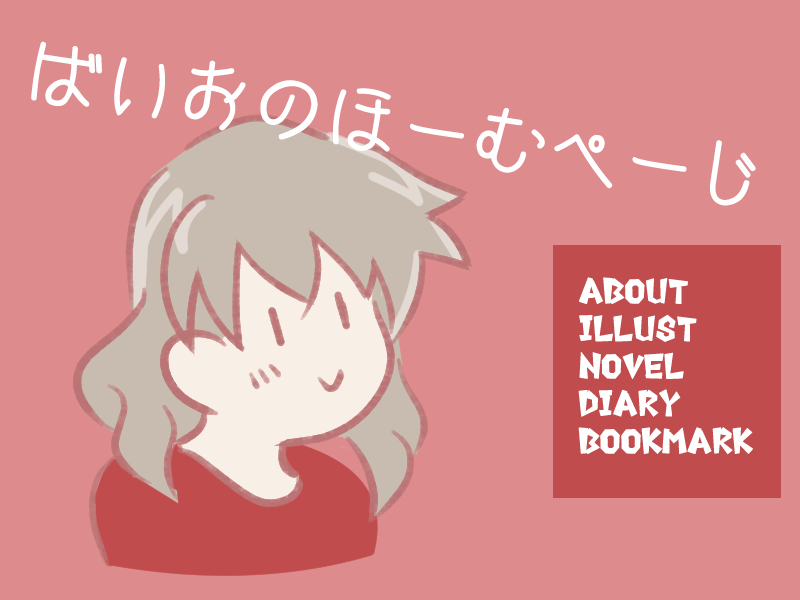
今と昔では個人サイトの定義が大分異なっていると考えたりします。今でこそSNSは疲れた人の休憩場所というイメージが強いですが、全盛期は創作者にとっては発信媒体のデフォルトでした。
私が個人サイトを開設した時期は中学生の頃で概ね世紀末の頃です。ここから数年間程度のデータの一部はInternet Archiveに現存しているため、時々読んで恥ずかしさに悶えます(笑)
自分は当時からPCオタクだったため、最初の一年程度を除きタグ打ちで一貫してました。今でもブログ以外の部分はタグを直接打つことが多いです。タグ辞典などの本も借りずにインターネット上の文献頼りでした。ほぼ独学ということになりますね…。
私が当時やらかした一番の失敗はコミュニケーション不良が多かったことです(ASDあるある…)現在は逆にサイトを軸にするという意味ではあまりコミュニケーションは取っていないため、結構真逆です。SNSですら余計なことは書かなくなったわけで、健常者に擬態できるくらい自分のことを書かない方が一番やりやすいと考えています…。
レスポンシブに関しては以前の就労継続の軽作業で覚えたこともあり、自分のサイトに実装した時期は割と最近です。作業に手をつけるまで知識がなかったんですよね…(スマホを持つ時期が比較的遅かったこともありますが)
レスポンシブなど比較的新しい技術を学んでサイトを作り始めた時期が大体2015年頃で、その後は創作のジャンルを変えるタイミングで一度閉じたりしつつ今に至ります。
当時の個人サイトに話を戻すと自分は比較的早く有料レンタルサーバーを借りていた記憶があります。(当時使っていた業者に学割があったはず…)当時は無料サーバーでも使えるパターンも多かったため、CGIについては積極的に利用していました。
“「ホームページをおくれよ」な注文に対して、(何かお仕事をした後に)その場でホームページのファイルを作って返すための仕組み
であり
Webサーバ上に置いてある(クライアントからの要求に応じて動く)プログラムを動かすための仕組み
です。”
Quoted CGIとは/Piyopiyo Create Service
当時はPHPよりCGI(というかPerl)が主流だったと記憶しています。掲示板や日記スクリプトは大体Perlで動いていたようです。Cで動いていたCGIはアクセスカウンターくらいしか記憶がないです(多分もう少しありますが、自分の手元にコンパイル環境がなかったため不明です)
コツを掴めば外観の改造くらいはできましたが、最近のスクリプトは外観の出力をスキン式にしていることがほとんどであるため、本体を弄ることは無くなりました。
スキンを改造する際もローカル環境を用意した方がいいことは今も変わらないですが…。
最近サイトを作り直した際に少し勉強をし直した所はありますが、基本はあまり変化がないため二十年以上タグを打っておいてよかったなーと思っております。
