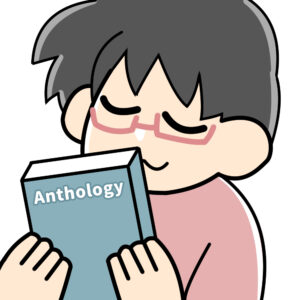
“アンソロジーってどんな本?
「このカップリング限定」「このシチュエーション限定」などのテーマを決め、大人数が寄稿する同人誌。5人以上の大人数が一般的。中には30人以上の大人数アンソロジーも。”
自分が寄稿した同人アンソロジーは30年ほど前に放送されたアニメのオールキャラ二次創作同人誌でした。(ちなみにここでちょこちょこ話題にしている作品とは別の作品です)
主催の方が初めてで手探りだったようで、発行にこぎつけるまでとても大変でした…と仰っていたことが印象的でした。
寄稿という形になるため、印刷データの様式については主催の方が利用する印刷会社に合わせることになります。(自分はうっかりミスをしてサイズだけリテイクになりました笑)
同人誌はコミックマーケット105で無事発行され、冬休みの終り頃に献本が到着しました。
個人的に感動したことは、20年以上前に一次創作で参加した時に後書カットを入稿し忘れてしまったため、当時のリベンジができたことです。当時はアナログ原稿がメインだったとはいえ、ものすごい失敗をしたなと思ってます。当時の本はもう手元にないですが、主催の方が自分だけ後書きカットを貰えてないと書いていて申し訳なかったですね。
他の方の作品を拝見するとバラエティに富んでおり、作品愛ってこういうものだよな〜と感じさせられます。
作品単位のアンソロジーについては、今年自分が二次創作で活動しているジャンルで行われるため、そちらにも参加する予定です。前回同じ主催で発行されたアンソロジーがかなり分厚いものとなったため楽しみにしてます。
アンソロジーにも色々あります
といっても、テーマの話ではなく。自分が直前に参加したアンソロジーはWebアンソロジーと言われる、テーマとなる作品のデータを主催に提出し一定期間主催のWebサイトで掲載するという形式を取っていました。
検索すると出てきますが(ブログのテーマ的にセンシティブ寄りかと思ったためリンクは省きます)、金銭的な負担が軽い代わりに管理が大変だそうです。展示期間が終了したら、寄稿者の作品の保護も考えデータを即削除!SNSにbotを設定していたらbotの設定を解除するのもまた責任なようです(XがまだTwitterの時に書かれた記事であったため、今はbotを使っている人は少ないかな…)
自分が寄稿者として参加した体感としては、他人にデータを渡す練習になったなと思います。データフォーマットやファイルサイズの規定はあると思われるため、そこをちゃんと理解できるスキルがあることは大事ではないかと思います。
最近だとネットプリントに出力するWebアンソロジーもあるとか…折角のデータが劣化するなど議論はありますが、理解のある方同士で行うならばありかもしれません。
