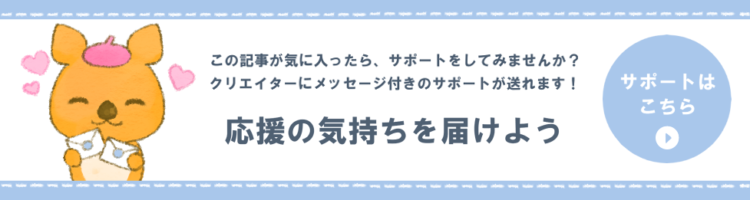健次郎は毎日、会社に行き仕事が終わると真っすぐ家に帰る。家に帰っても家族と会話があるわけでもなく、夕飯を食べ風呂に入って寝るという毎日の繰り返しに虚しさを感じていた。
健次郎はいつものように会社の帰りに電車に乗った。
ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン
規則的な揺れに疲れていた健次郎はついつい寝てしまった。
・
・
・
健次郎は駅員の声に起こされた。
「お客様、終点です。」
「あっ!すいません。」
慌てて降りた駅は薄暗く、人気の無い無人駅だった。
「おかえりの里・・・。知らない町だ・・・。」
駅の時刻表には始発の記載しか無い。
「しかたがない・・・。」
健次郎は駅を出ると商店街のような通りを歩いた。
何故か知らないと思っていた町に見覚えがあった。
「確かこの角を曲がったところに本屋さんがあったはず。」
健次郎はその角を曲がった。
そこには古びた古書店のような本屋があった。
「あっ、こんな感じだった。」
その瞬間、健次郎の記憶は小学生だった自分に戻った。
・
・
・
「ケンくん、遊ぼうよ~」
「うん、何して遊ぶ?」
「かくれんぼ!」
ケンは友だちとかくれんぼをしていた。
「も~い~か~い」
「ま~だだ~よ」
「も~い~か~い」
「ま~だだ~よ」
ケンは大きな銀杏の木の後ろに隠れた。
「も~い~か~い」
「も~い~よ」
そこからの記憶は消えていた。
・
・
辺りは白く朝靄が立ち込めていた。
健次郎はその大木のある場所に向かって歩いていた。
街はずれのわかれ道にあったその銀杏の木は黄色い葉を茂らしていた。
健次郎はあの頃と同じようにその木の後ろに隠れた。
・
・
・
「も~い~よ。」
ケンの記憶は小学生の頃の自分に引き戻された。
「ケンくん、み~つけた~。いっぱいさがしたよ~。」
「ごめん、ごめん、ボク、眠っちゃったみたい。」
「な~んだ。」
それからボクは自分の家?に帰った。
家には祖母がいた。
「おかえり、ケン坊。疲れただろう?ご飯食べてお風呂に入ってきなさい。」
みそ汁の匂いがする台所にいた祖母は優しく微笑んでいた。
ケンは祖母の作った夕飯は懐かしい味がした。
「この牛乳寒天、好きだったなぁ。」
薪で沸かした柔らかいお湯の風呂にゆっくり浸かった。
お風呂の柔らかい暖かさはケンを深い眠りに誘っていた。
ケンは久しぶりにゆったりとした時間を過ごしていた。
・
・
・
目が覚めた健次郎は電車に乗っていた。
車窓にはまぶしい朝日が差し込んでいた。
「ただいまー!」
家の玄関に着くと健次郎は元気よく言った。
「お帰りなさい。今日はずいぶんご機嫌なのね?何か会社でいいことでもあったの?」
妻が言った。
「いいや、おばあちゃんに会ってきた。」
健次郎はニコッとした。
「えっ?ああ、電車で眠って夢でも見たのね」
妻はニコッとした。