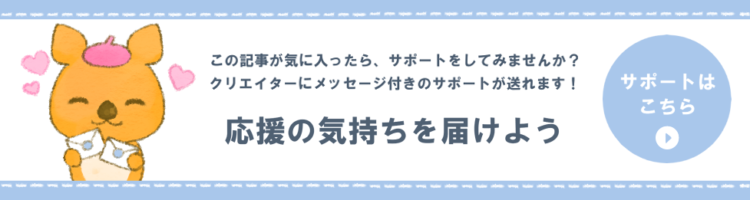…ある国の辺境の村に、それはそれは珍しい、花が咲いていました。
その花は、水に濡れると花びらが透き通る美しい結晶に変化するのです。そのことから花は「結晶花」と呼ばれ、辺境の村のシンボルとして、みんなで大事にしていました。
その花の世話係をしていたのは、イリゼという女の人。イリゼは毎日欠かさず花に水をあげています。おかげで今日も花は結晶に変化し、キラキラ輝いていました。
「イリゼさん、今日も水やりありがとう。」
「やっぱりイリゼさんが水をあげた時の結晶が一番キレイなんだよな。」
「そんな…ここのみんながあげれば同じですよ。」
「いや、イリゼさんの方が一番キレイですよ!いいな~。」
イリゼはそうは思いませんでしたが、村のみんなはイリゼが世話をした時が、一番結晶が美しいと口を揃えて言いました。
…そんな時、国のお城から第1王子様が護衛を連れて、村にやって来ました。
「ここが結晶花の咲く村か。はっ、何てボロい。流石は外れ者の村だな!」
「なんだと!」
「みんな落ち着いて。私が村の管理人ですが、今日はどのようなご用件でこちらへ?」
「結晶花を全て献上せよ。さもなくば、この村は全て焼き払う!」
「そんな横暴な!」
「お待ちください、王子様。結晶花は繊細な花。それにこの村の者が水やりをしなければ、恐らく花は結晶になりません。」
「そんなっ!?」
そう、結晶花は誰が世話をしても結晶になる花ではありません。どういう訳か、この村の者以外の人が世話をしても、結晶にはならずに透明な花びら、ただの花のままになるのです。これまでも沢山の行商人や職人が、結晶花の花びらを目的に村を訪れました。しかし誰も結晶のまま持ち帰った者はいません。すぐに透明な花びらになってしまうのです。
「むむむ…ならばこの村で一番結晶花を美しく咲かせる女を出せ!そいつを花と共に城に連れて帰る!」
王子が言い放った時、イリゼは真っ先に名乗り出ようとしましたが、周りの村人達が止めました。
「ダメです、イリゼさん!」
「そうだ、あんなヤツの言うことなんて聞かなくていいよ!」
「イリゼさんが…行くことない…!」
「私が行く。だからイリゼさんはここに…」
「みんな、ありがとう。でも、私が行きます。あとはお願いしますね。」
イリゼは、みんなにお辞儀をして王子の前に出ていきます。
「私が村で一番結晶花を世話している、イリゼです。」
「ほう…ならば結晶花の世話係として共に城まで来てもらおう。おい!他のヤツらは花の鉢を荷馬車に運べ!変なマネをしたら、この女と村がどうなっても知らんぞ!」
村人達は渋々、花の鉢を大事に荷馬車に運びました。そしてイリゼは逃げられないように腕を拘束され、まるで罪人のように王子の護衛に連れて行かれました…。
「イリゼさん…」
「花は種を保管しているが、イリゼさんは…」
「何とか出来ないんですか!?」
「イリゼさんだって村の一員だ!何とかしたいよ!」
「しかし…」
…一方、イリゼは拘束されたまま、辺境の村から馬車で10日かけてようやくお城のある都にたどり着きました。その間、固いパンと水しか与えられませんでしたが、イリゼは水を花にあげて、ずっと枯れないようにしていました。
お城に着くと拘束を解かれ、花を1人で全て荷馬車から降ろすよう命じられます。イリゼは黙って従いました。村人達と違い、城の兵士や護衛達では雑な運び方をして、花を散らしてしまうからです。
「7日後のパーティーで王族や貴族達にお披露目だ。それまでに最も美しい結晶花を育てろ。当然のことだが…枯らした時は、お前もお前の村の者も命は無いからな!…無事にやり遂げることができたら、次期王子妃として俺様の婚約者にしてやろう!どうだ?嬉しいだろう。泣いて喜んでせっせと働けよ!」
王子の言葉に、イリゼはただ黙って頷くしかありませんでした。
花を枯らしても、咲かせても、イリゼは村には帰れないと知り、花の世話をしながら毎晩声を抑えて泣いていました。その涙は、花を濡らして透き通った輝きを保ち続けます。
後編へ続く。