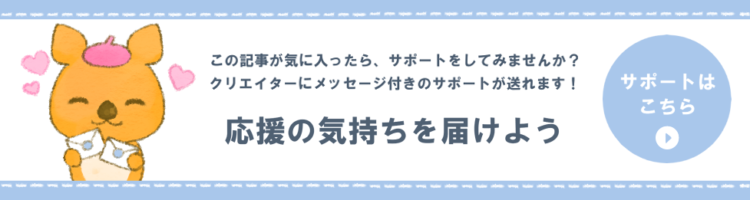「みるちゃん、ちょっとお使いを頼まれてくれないか?」
ある日、みるはむつぎから複数の本と封筒が入ったバッグを差し出されながら、そう言われた。実はこのお使いは初めての事ではない。そして、みるはこのお使いを頼まれると必ず嫌な顔をする。
「ええー・・・」
いつもは何だかんだ文句を言いながらも、むつぎのお願いを聞いてくれる、みるなのだが…これだけは本当にイヤな顔をして、イヤな声を出す。
「頼むよ、みるちゃん。」
「何でー・・・理由は?」
「最近向こうから来てくれなくて、溜まっちゃってるから。」
「むむむ~・・・ヤダ。」
「お願いだよ。おつりでイチゴのスイーツとか買っていいから。」
「私は子供か!」
「じゃあ、何でもひとつだけ言う事を聞くよ。」
「ん?何でも?ふふふ・・・わかった、わかったよ!行けばいいんでしょ!」
「流石みるちゃん!」
みるは、むつぎから奪うようにバッグを受け取り、図書館を出ていった。
みるが頼まれたお使い…それは、何らかの理由でページが見られなかったり、欠落していたりする本で「直せそう」と、むつぎが判断した本を「修理者」に持って行って直してもらうこと。
…実はこの本の「修理者」は、みるの師匠なのだ。みるからすれば、不思議図書館を紹介したのも、イミアとの出会いも(サラミは本当に偶然)、すべて師匠が黒幕。むつぎやイミアは尊敬しているが、みるにとって師匠は、実に食えない謎しかないヒトなのだ。
「・・・てか、あのヒトは探し辛いんだよ。まったく。」
師匠は常にどこかをフラフラしている。サラミのような気まぐれネコの行動よりもフラフラしていて、本の修理もたまに図書館に立ち寄った時に、まとめてやっていた。イミアに配達してもらえばいいと言った時もあったが、あのイミアでも捕まえられないらしい。
「会うと長いし、からかわれるし…もーう!」
モヤモヤしながら、みるはとある一軒家にたどり着き、ノックもインターホンもベルも無しに玄関のドアをおもむろに開けた。
「師匠ー!仕事の依頼ですよー!ってか、図書館に来て下さいよ!」
「…うーん、やっぱりみるには見つかるのね。」
玄関の先はすぐリビングになっており、そこには緩く長イスに座ってお茶をたしなんでいる人影・・・女性がいた。
…女性は凛とした芯の強そうな青い瞳を持ちながら、どこか不思議で怪しい雰囲気を放つ、魅力的な人。長くウェーブをかけた髪がサラサラ流れ、キラキラと陽の光で金の髪が何とも言い難い美しい色に光って見える。
彼女の名は「ユリドール」。通称ユリィ。
不思議図書館の本の「修理者」として、むつぎと仕事の契約をしているが、他にも色々な事を良いことから悪そうなことまで、おこなっているらしい。
「はい、むつぎからの依頼ですよ。」
「あらあら、わざわざ届けてくれるなんて…みるは優しいわねぇ。」
「…面倒くさいから来ないだけの癖に。」
「みる、仕事の代金が多いけど、これは私へのお土産ってことでs「ちーがーいーまーすー!!!」
みるはユリィがいつの間にかバッグを持っている事に気付くと、ガバッと急いでおつりの分をユリィから取り上げた。
「いいから早く仕事してください。」
「まあまあ、みるの近況も聞きたいわ。座って頂戴。紅茶のスコーンもあるわよ?」
「まーた師匠はそうやって…。」
「うふふ。それで、進捗はどう?」
「んー…まだまだって感じですかね。」
渋々みるはユリィの前の席に座ると、紅茶のスコーンに手を付ける。どこからかいつの間にか出てきたお茶も飲み始めた。
「貴女に不思議図書館を紹介して随分経つと思うけど。それでもまだまだなのね。」
「まぁ…むつぎも悪いやつではないし、イミアも凄いイイ子だし、サラミは…サラミはいいか。」
「みるの事だから、このままズルズルと図書館の助手になっちゃいそう?」
「なりませんよ。いつかは絶対に…。約束ですから。」
「・・・。そうよね、貴女はそういう娘だったわ。それだけは変わらないのね…」
ユリィは少し寂しげに、みるを見つめた。
「……いや、師匠!仕事!」
「はい、これでいいかしら?」
「早っ!!そもそもいつやったの!?」
「みるったら、それは貴女が良く知っているでしょうに。」
みるが中身を確認すると、ちゃんと全ての本が「修理」されていた。最後のページまで、しっかり読めるようになっている。
「寄り道せずに図書館に行きなさい。」
「師匠じゃないんですから、しませんよ。じゃあ、ごちそうさまでした。今度はちゃんと図書館に来てくださいよ!」
「はいはい。」
みるはバッグを確認して、代金をユリィに渡しバタバタと出ていった。
「慌ただしいわね…仕方が無い事だけれども。」
ユリィは紅茶のスコーンを1つ口にしながら呟く。それから紅茶の2杯目にシュガーをサラサラと入れる。
「あの娘の選択だものね。今度こそ後悔しないよう…私はあくまでサポートをするだけ。」
そう言って紅茶の2杯目を飲んだユリィの姿は、次の瞬間にはリビングから消え去っていた。

終わる。or クリップで留める。