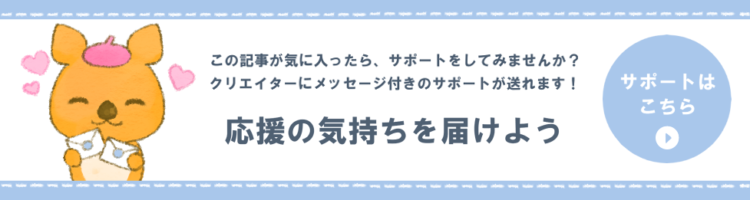※自作挿絵あり。
…2月と言ったら、何を思い浮かべるだろう。
節分?いやいや、大半がバレンタインと答えると思う。
バレンタインとは元々人物の名前(ウァレンティヌス)で、結婚を禁じられた兵士達の為に結婚式を執り行い、命令を無視したとして皇帝に処刑されたらしい。以後その日(明確には少し異なる)は、その人物に祈りを捧げる日とされた。
若者たちの「愛」を思った者から生まれた、バレンタインという日。カードや花束やお菓子を恋人や家族や友人達に贈るのが主だが、日本という国は女性が男性に「愛あるチョコレート」を贈るのが主流らしい。
そのせいか、みるの世界が2月過ぎになると、3人がみるの家に集まる時が多くなる。
そういう時の不思議図書館は、とても静かだ。居心地が悪い。司書の癖に、我ながら情けなくなる。昔はそうでもなかったのに。
「随分気持ちが柔らかくなったんじゃないかしら?」
「ユリィ様…。」
音も無く現れた修理者に驚くことはなくなった。慣れた、ということだろうか。
「貴方も楽しみじゃない?3人のバレンタインのチョコレート。みるの世界の男性は、だいたい楽しみらしいわよ?」
「…最近では「友チョコ」とか「自分チョコ」が主と聞きましたが。」
「それはそれ、これはこれよ。…ああ、これは私から。」
ユリィ様が取り出したのは、星やハートの一口サイズのピンク色のチョコ。イチゴのチョコを丁寧に袋に1つ1つ包んである。量からして3人の分も含まれているのだろう。
「・・・ユリィ様、思いっきり…みる贔屓じゃないですか。」
「あら?そう?」
知らんふりをしながらお茶を飲むユリィ様に、最早何も言う事はできないだろう。
「むつぎさーん。」
「むつぎー。」
そうこうしていると、運び屋のイミアと猫耳少女のサラミがやってきた。2人とも丁寧にラッピングされた包みを持っている。
「はい、バレンタインのプレゼントです!」
「まあまあ上手く出来たと思うよ。」
受け取った包みを開けてみると、イミアはガトーショコラ、サラミはチョコプリンが、崩れないように入っていた。
「ありがとう、2人とも。」
「ちょっといびつですけど…。あ、先生にもありますよ!でも、みるの家に置いて来ちゃって。」
「みるは、もうちょっと掛かるらしいから、アタシ達は先に来たんだ。」
「じゃあ私はみるを待っているわ。」
「あたし達は事務所とかに配って来ます!行こう、サラミ。」
「はいはい。…作るのを手伝ってくれたから、仕方なく付き合ってあげるんだぞー。」
相変わらず元気なイミアに手を引かれ、サラミも一緒に図書館から出て行く。それを見送るユリィ様と俺。
「ふふふ・・・」
「何ですか。」
「みるが来なくて残念そうだと思って。」
「まず残念という気持ちが、わからないんですが。」
「そうかしら?…今みるが来なくてモヤモヤしなかった?」
「…わかりません。」
やたら質問してくるユリィ様を無視して読みかけの本に手を付けようとした時。
「むーつーぎーーー!!」
ウワサをすれば何とやら。白いリボンを揺らして黒髪の少女が走ってくる。そして…
「くらえーい!!」
「ごふぅっ!?!?」
軟式野球のボール並みに硬くて丸い何かに「義理」と油性ペンで書いたらしい物体が、剛速球になって俺の頬に直撃した。座っていたイスごとバターン!!と倒れたが、誰も俺を気遣わない。いや、みるとユリィ様に俺を気遣うなんて、多分頭にないと思うのだが。
「みる、そんなどうでもいいことに魔法を使わないの。」
「いやいや、師匠に言われたくないですし!…あ、イチゴのチョコ!ちゃんと星とハートだ。ありがとう、師匠!」
「あら、イミアとサラミの分も入っているんだから、独り占めはダメよ?」
「はいはい。んじゃあ、またねー、むつぎー。」
「チョコ置いておくわよ、むつぎ。」
そう言って、嵐か何かのような2人は去っていった。俺は起き上がってイスを立たせ、改めてみるが投げつけてきた丸い何かをまじまじと見る。
完全にカチカチの硬い何かだ。チョコの匂いはするが、食べられそうにはない。
「多分だが、こうしろってことだろうか・・・。」
俺は道具箱からハンマーを取り出し、思いっきり振り下ろしてみた。
何か、は真っ二つに割れてくれたが、中もチョコの匂いがするだけ。
「うむむ・・・」
困る。が、俺は割れた物体を更に砕いた。砕き続けた。その結果…
あった。薬のカプセルのような、小さな小さなプラスチックの物体が。
それを開けると、ようやく食べられるチョコらしいチョコが、コロンとテーブルの上に転がった。
「一口…よりも小さい。」
あんなに時間がかかったのに、割に合わないチョコを口に入れる。
「・・・・・苦っ!!」
とんでもなくブラックな、ビターチョコだった。

…
一方その頃、みるの家ではユリィとみるがテーブルに各々のチョコを並べて、お茶を飲んでいる。
テーブルの端には、綺麗にリボンを付けたハート型のチョコレートが置いてあった。
「はぁ…。今年も、渡せなかった。」
「仕方がないわ。また、保管しておきましょう。」
「うん…。」
みるはハート型のチョコをユリィに手渡し、受け取ったユリィは大事にそれを仕舞う。
「でも、こんなに溜まっちゃったら…いくらビターでも嫌になっちゃうよね…あはは…。」
「・・・そんなことないわ。彼は貴女の手作りなら、時間をかけても1人で全部食べ切るわよ。そういう男でしょう?」
「・・・うん。」
みるは両手をギュッと握り、顔を下向きにして涙をぽろぽろ零していた。
「みる。…私しかいないわ。思いっきり泣きなさい。」
「っ・・・うわあああん!!会いたいよ…早く会いたい!!どこにいるの…約束したのに!!ずっと一緒にいるって!!一緒に生きるって!!ぐすっ・・・」
ユリィはみるが落ち着くまで、彼女に胸を貸して頭を撫でてあげた。
バレンタインのチョコをあげたい彼の代わりには、なれないけれど。
貴方の気持ちがわかるのは、自分(ユリィ)だけだから。
終わる。or クリップで留める。