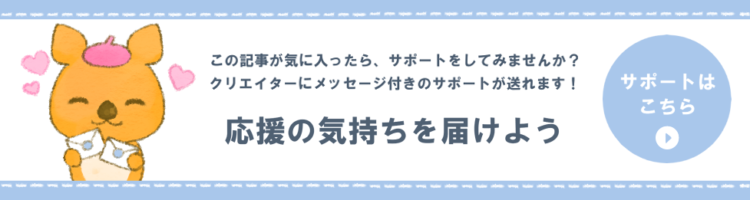…これは、後に不思議図書館の常連となる少女・みるの過去の一部。
魔法の無い世界で外れ者だった少女は、10歳で家と自分の世界を出て、沢山の世界を巡った。
とある世界に行った時、少女は先祖の魔導師の弟子に出会い、自分に女神の力がある事を教えられる。
少女はしばらく弟子の所で、しっかりと魔法を教わる事にした。
たくさん、たくさん、苦労した。
女神の力は人間の少女には負担が大きすぎて、何度も何度も気絶することがあったり、魔力が多すぎて熱を出すこともいっぱいあった。
それでも、少女は魔法をやめたりしない。今までずっと、自分や周りを助けてきたのも、魔法だったから。
『お前の力は、生と死、太陽と月、どちらにも傾かない。2人が願った結果生まれた力…生を願う者、死を望む者、どちらの「願望」も叶える「星の力」だな。』
『星の力…。』
少女は、少しずつ女神の力である「星の力」の練習もしつつ、また身体に負担がかからないようにする補助の道具や武器の作成にも取り掛かる。数年後、少女は弟子に認められる程、魔法が上達した。
そこで、成長した少女はまた旅を始める。今度は自分の将来を考える旅。少女は人間。人間の身体のまま女神になるか、本当に人ならざる者として女神になるか、女神を放棄するか…。放棄すれば当然「星の力」は使えなくなるのだ。
少女は悩みながらも、星の力を使って困っている者達を助けていった。
…そんなある時、少女は救いを求める「黒い羽根」と出会う。
少女は黒い羽根に導かれて、ある世界に降り立ち、1人の男性に出会った。
20〜25歳くらい、身長が190センチ程で、銀色の長い髪を纏めている、目つきの鋭い、刀を使う美男。
少女は最初こそ怖くて近寄りたくなかったが、男性が救いを求めてきたと思うと、話しかけずにはいられない。
そして、案の定「なんか力が強い小さい娘」として男性に捕まった。
「オレの周りをウロチョロして…何なんだ、お前は。」
「私は、貴方を救いに来たの!」
やっぱり、頭のイタい子扱いされた。
でも「なんか力が強い」というのは男性も引っかかっていたらしく、男性はしばらく少女の監視として共に居住することにした。
「また外に放って兵士に捕まっても面倒だからな。」
「普通の人間になんか、捕まらないもん。」
「ふん、どうだか。」
「むっ、何かバカにされた気分。見ててよ!」
少女は襲ってくる辺りの魔物…モンスターを魔法で倒してみせる。
「どう?」
「…それがどうした?」
男性は刀で少女以上の数のモンスターを倒した。
「これくらい朝飯前だ。」
「むー!今に見ててよ!ぜーったいに負けたって言わせてやる!」
しばらく一緒に生活していると、男性はどこにも属さない傭兵で、依頼があるとモンスター退治や戦争に行くこと、強すぎて憧れもされるが、恐怖もされていること、人付き合いをしようとしないことが少女にもわかった。
「私も一緒に行ってサポートする!…戦争とかは行かないけど、モンスター退治なら大丈夫だし!」
「お前な…だいたい、その黒髪で付いて来られたら逆に怪しまれるだろう。」
「じゃあ、こうして…。」
少女は魔法で髪の色を金色にし、2つに結んだ状態にした。更に服装も変える。
「これでどうよ。」
「……。名前は?■■ のままで通すつもりか?」
「ミィ。それか、ルティナリス。私が色んな世界で使ってきた偽名。どっちでもいいよ。」
「……ミィ・ルティナリス…「ミィ」だな。言っておくが、オレの助けは期待するな。」
「レフィこそ、私の過剰な助けを期待しないでよ?」
「レフィ?」
「あだ名だよ。「レフィール」なんだから、レフィでいいでしょ。」
「……勝手にしろ。」
こうして、その日から少女は「ミィ」として、男性「レフィール」のサポート役をすることになった。おかげで、わかった事がある。
皆がレフィールの人間離れした強さ・速さ・体力について行けないこと、レフィールの討ち漏らしを察知出来ず、結局全部レフィールが倒していること…それと…
美男なせいで、女性にモテていること。
それら全て、少女…ミィがサポートに付いたことで改善していった。
ミィの魔法はこの世界には無い、ミィだけの魔法。そしてレフィールは確かに刀での攻撃は強力だったが、魔法ではミィに及んでいない。魔法でならミィはレフィールに並ぶことが出来た。
レフィールの討ち漏らしや、魔法が苦手なモンスターはミィが倒し、同じ傭兵や協力者へのフォローをし、レフィールへの女避けにもなったのだ。
そんな日々を繰り返していたある日。ミィとレフィールは報酬で大量の銀を貰う。
「お前の武器でも作るか?」
「そんなこと言われても…あ!そうだ!銀の女神・シルは確か鎌を使っていた筈。」
「お前の前世の女神の1人か…。」
「杖は普通の素材じゃあ無理だと思う。だったらそっちがいいかも!」
「わかった。」
レフィールは銀を良い鍛冶屋に持って行き、オーダーメイドで鎌を作らせた。自分の刀と同じくらいの切れ味のものを。
数週間後、立派な大鎌と羽の形のネックレスが届く。
「?…レフィ?こっちのネックレスは?」
「それは、お守りだ。」
レフィールはミィの手を取ると、ネックレスを握らせ両手でその手を包んだ。
「一緒にいてくれて…その…感謝している。今までずっと1人だったからな。だから…これからもオレの傍にいてくれないか、■■。」
「レフィ…!!私も、一緒にいたい。これからも…いていい?」
「ああ、もちろんだ。」
レフィールがミィの頭を撫でると、ミィは心地よさそうに微笑み、レフィールも気付けば微笑んでいた。
後編に続く。