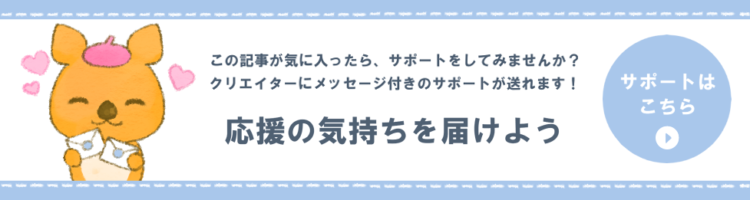かつて栄華を誇った文明たちも、今ではすっかり草木に覆われている。まるで終わりゆく世界に、自分だけが取り残されたような気分になる。……いや、私は取り残されたんだろう。こうしてヒトとして生きていると、自分が何者かを忘れそうになる。何のために生まれ、何のために生きるのか、その使命すらも……。
今晩の宿を探そうと、朽ちかけたビルに入った時だった。
≪彼ら≫以外の気配を感じ、足元に気を付けながら、ゆっくりと階段を下っていく。最後の一段を下りきると、軋むドアを開けた。
円柱形の水槽の中に人形の何かが見えて、思わず駆け寄った。それは検査着を着た少女のようだ。彼女は、人なのだろうか、人とはこのようなものだったろうか……。ジロジロと彼女を見つめていると、彼女の閉じられていた瞼がゆっくりと開いていく。瞼を擦ったあと、大きく伸びをしている。
「おはよう、いや、こんばんは、かな」
私は掠れた声で彼女に話しかけた。彼女は私に気付くと、驚いたように目を見開く。そして、とびきりの笑顔を私に向けると、何かを指差しパクパクと口を動かした。彼女の指さした先を視線で追うと、そこには簡素な機械が置かれており、機械のレバーはクローズにあわさっている。レバーから彼女へと視線を移すと、首が取れるんじゃないかとばかりに、上下に振っている。
「そこから出たいんだな?」
私は暫く考え込んだあと、その機械に近付き、また水槽の中の彼女を見上げた。彼女は縋るような目で私を見つめ、何度も何度も頭を下げた。私は恐る恐るレバーを握ると、グッと力を入れオープンへとあわせる。地響きのような音と共に中の水がどこかへと流れ出ると、ゆっくりと円柱形の水槽が地面へと潜っていく。彼女はしっかりとその両足で大地を踏むと、私に駆け寄ってきた。
「ありがとう、お兄さん! 私、イブ! 貴方は?」
そ、そうか、はじめまして、彼女の赤い髪をくしゃくしゃと撫でながら、少し屈んで彼女に視線を合わせた。
「私は、アダム、ただのアダムだ」
アダムとイブ、その名前に何か運命的なものを感じたが、それ以上に久々に会えた人に私達は舞い上がった。イブはクルクルと踊るようにして、辺りを飛び跳ねながら外に出れたことを喜んでいる。嬉しそうに笑うイブを見ていると、心のどこかが温かくなる気がした。