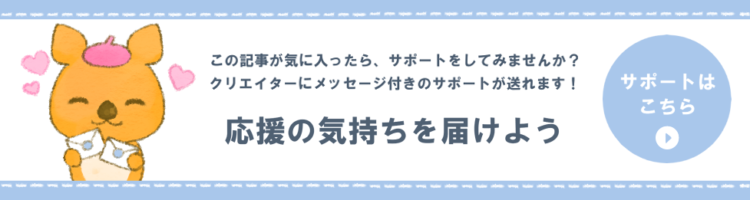地下から階段を上り地上へ出て、ふと夜空を見上げた。わぁ……、とイブが感嘆の息を漏らすのを横目で見つめると、見慣れた満点の星空をぼんやりと眺める。
「きれい……、写真より絵より、ずっとずっときれい!」
ゆらゆらと揺れるランタンの明かりに照らされて、イブの目が星のように瞬いた。私が散々見飽きた星空も、彼女にとっては真新しく、そして素晴らしいものに見えているのだろうか?
「ありがとう! アダム」
星空から私に視線を移すと、イブは満面の笑みを向ける。暫くなんと返せばいいのか分からず、ただじっと黙り込んでいると、呆然と立ち竦む私の隣にイブは腰を下ろした。
「私、あそこでずっとずっと一人ぼっちだった、もしかして、アダムもそうなの?」
すっと私を見上げるイブに、私はゆっくりと頷いた。そうなんだ……、どこか少し残念そうに笑うイブを見て、私は、《本当の私》について、きちんと話す決心をした。
「なぁ、イブ、少し聞いてくれるか? 私は、……君が思っているような《人》じゃないんだ」
どういうこと? 首を傾げるイブに、私は少し口ごもりながら、私は、造られた存在だということ、本当の《人》は随分前に人としての役目を終えていること、を話して聞かせる。
「人は、どこに行ったの?」
イブは真剣な目で私を見つめる。私はイブの手を取り、ランタンをもう片方の手にビルから出ていくと、辺りに佇む彼らを指さした。
「あそこに居るのが、人だ」
皆一様に目と口を閉ざし、後頭部付近から赤い花を咲かせた彼らを、私は人と呼んだ。イブは私と彼らとを見比べたあと、私の手を振り払い彼らに駆け寄っていく。イブの寂しそうな声だけが、しんと静まり返った都会に鳴り響いた。
アダムとイブ、人類、始まりの二人の名前をつけられた私達が、人類、終わりの二人だなんて信じたくなかった。
「イブ、彼らは、もう……」
私は泣きじゃくるイブの肩に手を置いた、イブは私を振り返りキッと睨み付ける。無いはずの心が、ズキリと痛んだ。
「こんな、こんなことなら、私、ずっと、ずっと一人でも良かった!」
彼女の夢を、希望を、私は無慈悲な現実で打ち砕いた。子供のようにわんわんと泣く彼女を、どうやって慰めればいいのか分からない。彼女を突き放すことも出来ない、彼女を抱き締める権利もない、私はただただ、彼女が泣き止むまで、ぼうっと見つめ続けた。
この世界から人が消えた何日目かの朝、私は寝息を立てる彼女を一人おいて、どこか重い足を引きずるようにして歩いていた。
「……私は、出来損ないだ」
人によく似せた体と頭を持っていても、唯一出会えた友を慰めることすら出来ない。一人きりで生きるのに慣れてしまって、人を思いやる心すら捨て去ってしまったんだろうか……。
「私には彼女が必要だ、でも……」
彼女には、私は必要ないかもしれない、そう頭に思い浮かんでも、言葉にすることが怖くて、私は言葉の代わりに、ため息をついた。
「彼女、イブ、次第だ」
私は背負っていたリュックから、古ぼけたラジオを取り出した。ダイヤルを回し、周波数を合わせると、誰かの声が流れ出す。
「……彼にイブを託そう」
悲痛な叫びにも似た誰かの声と、昨夜のイブの泣き声が自然と重なった。彼は、人だ、偽物の私とは違う、本物の、人だ。
「人擬きより、ずっといい」
ラジオのスイッチを切り、リュックの中にしまい込むと、重かった足が、少しだけ軽く思えた。