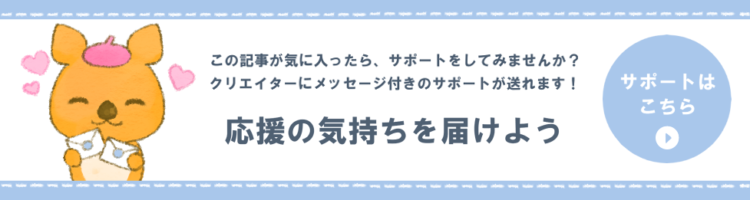私は見晴らしのいい小さな丘の上に立つと、辺りをぐるりと見回した。耳をそばだてれば、生き物の息遣いが聞こえる、目を細めれば、生き物の姿形がはっきりとこの目に映る。すぐ側を牡鹿が跳ねていった、私は物陰に隠れると持っていたナイフを取り出す。今日は弓を使える自信がない、あまり得意じゃないが、ナイフで仕留めるしかない。血に塗れた私を見てイブは一体どう思うんだろう?
頭を振って邪念を払う。浅く早く吸って吐いてを繰り返し、汗で滑るナイフを握り直した。のんびりと草を食む牡鹿に忍びより、一気に間合いを詰めるとその喉元をナイフで切り裂く。甲高い鳴き声がした。見れば仔鹿が牡鹿をじっと見て、ふるふると小さな体を震わせている。
「……」
私は弓に矢を番えた、もう随分と慣れた狩りだ。狙いは外さない。へたり込んでいる仔鹿に狙いを定め、息を吐き出すと同時に矢を放った。
牡鹿を捌き終えると、ふと赤く染まった自分の両手が見えた。このままの姿で彼女に会いたくない、ぐるりと辺りを見回し水場を探すと、どこからか水の流れる音が聞こえた。捌き終えた獲物を背負うと、ゆっくりと音のするほうへと歩き出した。
小川に自分の姿を映すと、思わず苦笑いした。白い髪も肌も全て赤く染まっている。服のままざぶざぶと小川に入ると、辺りの水面が赤く濁る。着ていた上着を脱ぎ、布同士をこすり合わせるようにして、少しでも血が薄まるまで洗い続ける。
「これくらいか」
石鹸の一つや二つあればよかったが、残念ながら私に石鹸を作るような知識はない。薄茶色に染まった服を絞ると川岸に乾かし、もう一度小川の中へと入っていく。全身を洗い終えた頃にはあれほど高かった日が、すでに傾き始めていた。
「……長居しすぎたな」
ふと何かの気配を感じ辺りを見回した。見れば血の匂いにつられたのか、肉食獣の群れがこっちへとにじり寄ってきている。手早く身支度を整えそこから離れようとしたとき、見覚えのある人影を見つけ慌てて駆け寄った。
「イブ! 何でここに?!」
半泣き状態のイブの肩を掴み、思わず声を荒げてしまう。また、一人になるのは嫌だったから……、ボロボロと両目から涙を零すイブを見て、はっと我にかえる。私はあまりに馬鹿だった、一人きりであんな場所に居た彼女を、また一人きりにしてしまった。もし自分が同じ状況に置かれたら、彼女と同じように私も探しに行っただろう。
「私が悪かった、すまない……」
小さな子供のように泣きじゃくるイブの頭を撫でる、少しくすぐったそうに笑うイブを見て、ほっと胸をなでおろすと、辺りを取り囲む肉食獣へと向き直る。
リュックからナイフを取り出し構えると、大きく息を吸ってゆっくりと吐き出した。一斉にとびかかってくる獣達を、大きく上に飛んで躱すと、一頭に狙いを定めその頭をナイフで刺す。自重をかけ深々と刺さったナイフを抜くと、大きな体がゆっくりと地面へと倒れていく。荒くなった息を整え、次の一頭に狙いを定めるとナイフを投げつけ、獣の目元に刺さったナイフを柄を握り強く押し付ける。二頭の獣を倒したところで、ほかの獣たちが蜘蛛の子を散らすように逃げ去っていった。
「……大丈夫?」
イブの心配そうな声に、私は彼女を振り返り小さく頷いた。後ろを向くように言うと、イブが後ろを向いたのを確認してから、今さっき倒したばかりの獣を手早く捌いていく。使えそうなものと食べれる分だけ選り分けると、体を震わせているイブの肩を叩いた。
「は、はい!」
もう夜だから帰ろうか、私が笑いかけるとイブはぎこちなく笑って頷く。あと少しだけ待っていてくれ、ナイフの血をはらい、捌いたばかりの肉を両手に小川につかると、肉と自分に付いている血を落としていく。
「いつもこんな事してたの?」
背後から声を掛けられ振り返る、寒いのか、それとも、怖いのか、いまだに体を震わせるイブを見つめたあと苦笑しながら頷いた。もし私が完全な機械仕掛けなら、こうして他の生き物を殺める必要もないし、死を、機能停止を覚悟して、狩りをする必要もない。
だが、この体は、人に限りなく似せて作られているからか、ロボットとは違いあまりに不自由なことが多い。疑似人体とも言える自分の体に、はじめ戸惑うこともあったが、もうこうして何年も過ごしていれば、嫌でも慣れてしまった。
「さぁ、帰ろう」
小川から出て獲物をリュックにしまいながら、イブの手を取って歩いていく。昨夜あれだけ星空を見てはしゃいでいたイブが、今日はただ黙り込んで私に手を引かれながら歩いている。今、私とイブの間には大きな溝が出来た、だが、私は頭を振りそれを無視した。