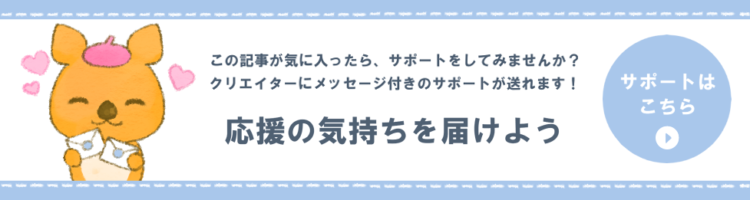二人寄り添って昨日の残りを食べていると、イブが赤くなった両手を擦っている。長時間弓矢を使っていたせいだろう、小さなマメが手のひらにできている。痛い……、少し涙ぐむイブに、頑張った証拠だ、と頭に手を置いてぐしゃぐしゃと撫でた。
「もう! すぐ子ども扱いする!」
ぷくっと両頬を膨らませるイブに、悪い悪いと笑いかける。弓矢のメンテナンスをしていると、興味津々といった様子でイブが覗き込んできた。危ないから離れて、と声をかけてもお構いなしに、じっと黙って私の手元を眺めている。
「器用だね、自分で作ってたんだ」
そっちのほうが愛着も沸くからな、一通りメンテナンスを終えてから、ごろりと横になった。それにしても、一人じゃないというだけで、これだけ一日が早く過ぎるとは思わなかった。いつも、同じことの繰り返しで、このまま一生を終えるのかと思っていた。
「えっと、あの……、今まで、ごめんね?」
空を眺めていた私の顔を覗き込むようにして、イブが深々と頭を下げてきた。何に対して謝られたのか分からず黙り込んでいると、イブは慌てた様子で次から次へと言葉を吐き出す。
「私、わがままばっかりだった、自分のことばっかりで、アダムのこと全然考えてなかった」
よほど心苦しいのかイブの目から涙が零れた、私は手を伸ばしてその涙を指先で拭うと、別にいいんだ、と出来るだけ優しく笑いかける。私だって彼女のことを考えていたつもりではあったが、それが全く自分のためではないとは言い切れない、それに出会ってまだ間もない二人が何の衝突もなく一緒にいられるなんて夢は抱かない。
「まだ答えは先でいい、だけどよく考えてほしい。私は、イブ、君に幸せになってほしい。友として、仲間として、君の幸せを願っているんだ。君には君だけの人生がある、君の選択を阻むものは何もない、君は、もう、自由なんだ」
イブは真剣な顔で頷くと、私のすぐ隣に横になった。互いに顔を見合わせると、イブは照れたように笑う。じんわりと胸が熱くなる、彼女に出会った時に感じた、あの温かい気持ちが胸いっぱいに広がっていく。おやすみ、イブに声をかけ、背を向けると目を閉じた。