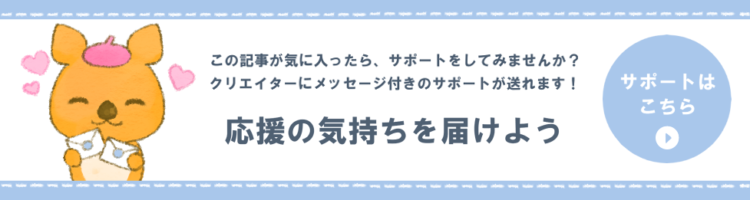あれから大分経ったある日の事、唐突にイブが海を見たいと言ってきた。静まり返ったビル群から離れ、時折狩りをしながらゆっくりと歩いていく。あの一件があってからイブは狩りの腕前を上げ、私がいなくても一人で獲物をとってくるようになっていた。
「なんか変な臭いしない?」
イブが鼻をつまみながら呟いた、海が近いんだよ、私が笑うとぱぁっと顔を明るくする。長い時間旅をしてきたが、イブと海に行くのは初めてだった。写真や絵では見たことがあるといっても、実際に見るのとはまるで違う。イブが走り出したのを見て、苦笑しながら私もその背を追った。
眼前に広がる海を見てイブは目を見開いた、すごい! 広い! あとあと! イブは子供のようにはしゃいでいる。押してはよせる波を見つめると、私と海を見比べる。
「いっておいで」
私が声をかけるより早く、イブは砂浜を駆け出した。バシャバシャと水を蹴りながら笑っているイブを見て、自然と笑みがこぼれる。イブに手招きされ、暫く考え込んでから、恐る恐る海に足をつける。大丈夫そうだ、ほっと息をついた私を見て、ニヤリとイブが笑った。
嫌な予感がする、バシャッと音がして、海水をもろに浴びるとイブを睨んだ。
「こっちまで来てみて!」
ざぶざぶと海の中に入っていくイブを見て笑っていると、突然その姿が波間に消えてしまった。慌てて海の中に潜ると、イブは魚達を見て目を輝かせている。はっと我に返ると、体が海の底へと沈んでいく。口から息が漏れ出し、泡となって浮かんでいった。
負荷が強いのか、視界がチカチカと光り出す。重い腕をなんとか海面へと向けると、ひんやりとした誰かの手が私の手を握った。
途切れがちに誰かが私を呼んでいる、泣きそうなその声は、どこかで聞いた事がある気がした。大切な誰かだった気がする、大切な思い出があった気がする、だが、よく思い出せない。頭に靄がかかったようになって、体がひどく重く感じる。
「アダム! ねぇ、起きて、起きてよ!」
必死に私を呼ぶ誰かの声にこたえようと、口を開いた瞬間体内に入った水を吐き出した。ぼんやりとした視界が鮮明になり、ボロボロと涙を流すイブが私を見つめている。
「……イブ」
ごめん、ごめんなさい! 涙を流しながら謝るイブを、私はただぼうっと眺め自分の手を見た。砂にまみれた自分の手を、謝り続けるイブの頭に置いた。ころころと表情を変えるイブといると、どうしても冷静でいられない時がある、一人きりの静かな毎日が少しだけ懐かしい。だが、これでいい、孤独な日々よりはずっといい。
「体、大丈夫?」
漸く泣き止んだイブが私を見つめる、両手を閉じたり開いたりしてから、あぁ大丈夫そうだ、力なく笑って見せた。そっか、良かった、ほっと息をつくイブが、ふと海の方へと目をやった。その視線を追うと沈みかかった日が、空と海を橙色に染めている。
「ここに来れてよかった」
夕日を眺めながらぽつりと呟く、うん、本当に、イブの満足そうな声を聞いて笑う。初めて会った時から大分経った、イブが叶えたかった事ももう残り少ない、間もなく別れの時が来るのを一日が終わるたびに実感する。それでも、あと少し、もう少し、一緒に居たい、親友とも、恋人とも、家族とも違う、どこか歪な関係でも私にはイブしかいない。
「なに、考えてるの?」
イブはまっすぐな目で私を見つめる、私はその目から逃げるように空へと向けた。イブはしばらく黙り込んだ後、会ってから、とモゴモゴと言い淀んでいる。
「もし、私たち以外の人がいるなら、私はその人に会ってみたい。会って聞いてみたいの、この世界に何が起こったのか、なんで人はあぁなったのか」
イブの力強い声に私は何も言えなかった、否定も、肯定も、したくなかった。もう彼女が心を決めていたとしても、私はまだ彼女と旅を続けていたかった、世界のありとあらゆる景色を彼女に見せたかった、そしてこうして語り合いたかった。
でも、それは私のエゴだ。彼女はもう先に進もうとしている、彼女は私から巣立とうとしている。彼女を縛り付けているのは、彼女と離れがたいのは、私だけだ。
「……会いに行こう、彼に」
エゴを捨て去ることなんかできない、こんな時自分がただのロボットだったら、感情もないプログラムの羅列だったら、と願わずにはいられなかった。苦しい、心が苦しくて仕方ない、永遠に続く幸せなんてない、そんな事は分かりきっていた筈なのに辛い。
「そんな悲しそうな顔しないで、まだ会ってみないと分からないんだから」
励ますような、困ったような声、私は彼女に背を向け寝転んだ。自分らしくないと分かっている、出来損ないの紛い物のくせに、人のためにと作られたのに、私は彼女を苦しめている。涙すら流せない不出来な自分を、彼女は大切に思ってくれているのに、ズキズキと胸の奥底が痛んでも、なにもかも作り物でしかない、私は、私が嫌いだ。