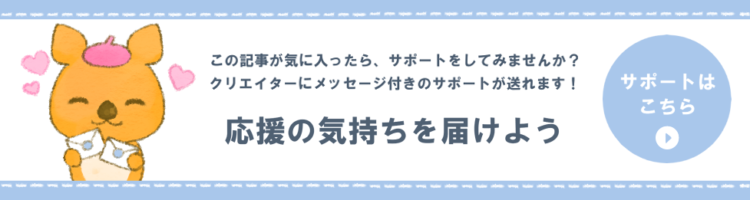あの依頼以来、三人はどこかぼうっとすることが増えた。ある種霊能力者を生業とするものとして、霊がいること自体が普通のことだと思っていたが、あの女のように気を病んで見えない存在として霊を妄想することもある、ということに衝撃を受けていた。
「……あの人、大丈夫かな」
誠がポツリと呟くと、二人は答え代わりにため息をついた。特に自分たちが何かをした、というわけではないのにもかかわらず、依頼料を貰った事に対してもどこか罪悪感がある。かと言って、自転車操業である事に変わりなく、辞退するほど余裕があるわけでもない。三人は悶々としたまま、次の依頼を待っていた。ノックが聞こえると、暫く考え込んだ後、どうぞ、といつものように誠が声をかける。快活そうな若い男が、三人を見ると小さく頭を下げてきた。男は依頼者用の椅子に座ると、ハキハキとした声で話し始める。
男のアルバイト先である、とある遊園地のお化け屋敷に、どうやら本物が混じっているらしい。お化け屋敷から出てきたお客が、次々にあそこが怖かった、あの髪の長い女の人は名演技だ、などと口々に言うのを聞いて、お化け屋敷のスタッフは首を傾げた。怖いと評判の箇所には、特に仕掛けがあるわけでもなく、髪の長い女が怖かったというが、お客から聞く見た目をしたスタッフは一人もいない。だいいち、女が現れるという場所には、お化け役のスタッフが隠れられる場所はないという。
「ね、気味悪いでしょ?」
どこか能天気にも思える男は、一通り話し終えると目をキラキラと輝かせた。誠は男にどこか自分を重ねると、思わず苦笑してしまう。二人からしたら、きっと自分もこう見えているに違いない、そう思い二人を振り返ると二人もまた苦笑している。
「遊園地側には話が通ってるから、心配しなくて大丈夫っす」
ニカっと笑う男の白い歯が眩しい、今まで来た依頼者の中で一番健康で、なおかつ心霊体験とは程遠いその男を見て、どこか三人はほっとした。男が言う遊園地の名を聞いて、三人は思わず目を見開いた、そこは県内でも有数のテーマパークだったからだ。住所は、メモらなくていいっすかね? けらけらと笑う男を見て、三人は顔を見合わせた。
依頼者が帰ったあと三人はそれぞれお化け屋敷についての口コミを調べ始める。どうやら心霊スポットとしても有名になっているらしく、休日にもなると長蛇の列ができるほど人気らしい。心霊に関する創作物には、必ずと言っていいほど、本物が引き寄せられるとはよく言うが、ここもまたそんな場所の一つなのかもしれない。
「遊園地なんていつぶりだろ? ね、ね、私もついていっていいんだよね?」
キラキラと目を輝かせる梓に、誠と玉藻は互いに顔を見合わせる。ほぼ同時に二人が頷くと、梓はぴょんぴょんとその場ではねた。仕事に行くんだからね? と釘をさす誠に、私はここの局員じゃないから、と梓はニヤリと笑いかけた。