「噓をまとめたジョンカラ節」か!?
青森・「東日流外三郡誌」
(つがるそとさんぐんし)
を検証する
ライナス
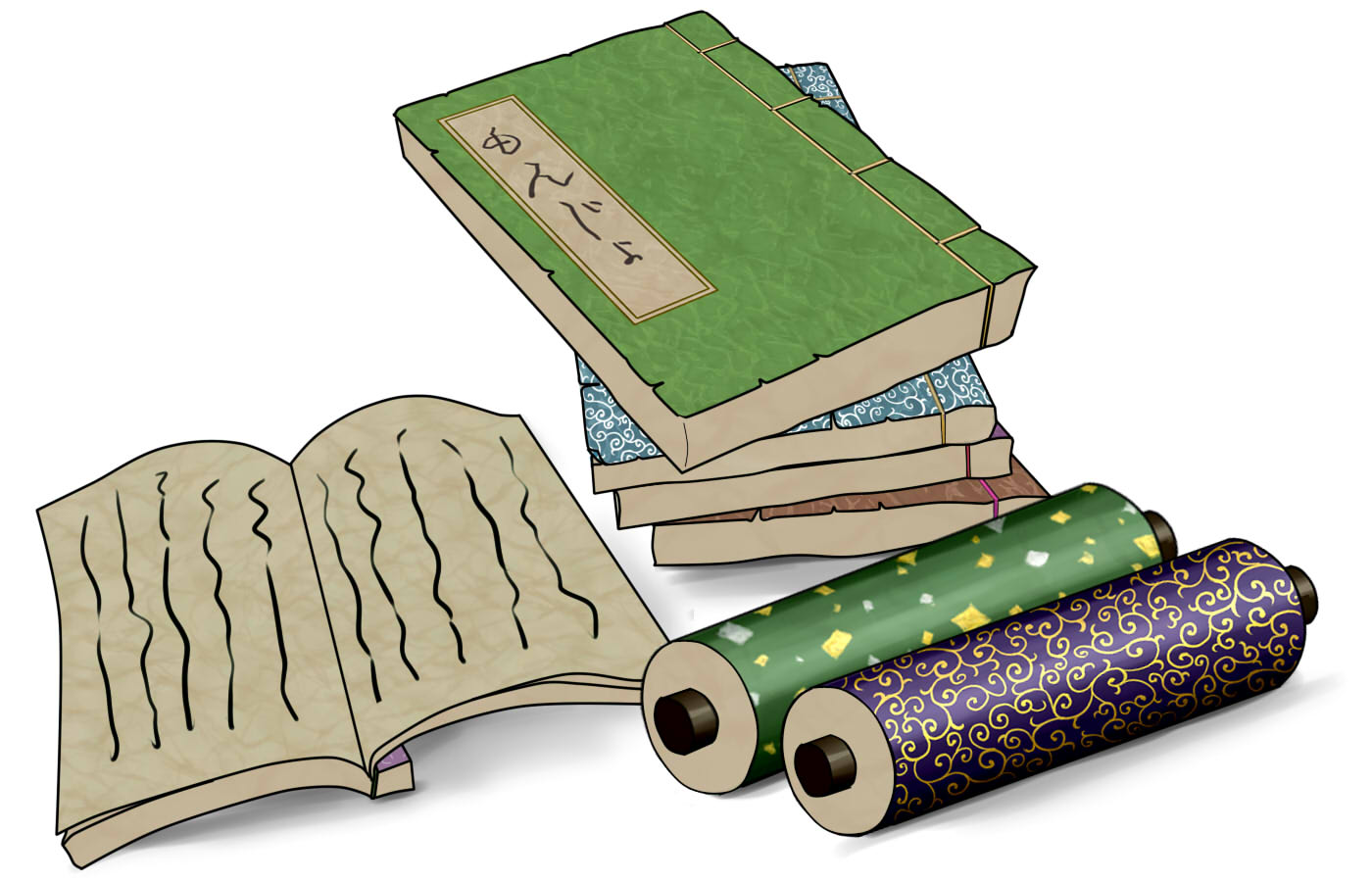
訴訟の結果は法曹界特有の
「玉虫色の判決」に…。
このように「偽書派」の指摘が正鵠を得ていたのに対して、「擁護派」(「真書派」と呼ばれていますが、ここでは「擁護派」と書きます。)も反論を開始しますが、ほとんどが的外れで、揚げ足取りにもならない牽強付会の妄説を繰り返すのみで、最初は関心を寄せていた大手メディアも、徐々に潮が引くように報道から撤退していきました。
その最中、1995年2月、大分県のアマチュア歴史研究家から訴えられていた訴訟について、青森地裁で判決の言い渡しが行われました。
「裁判所」が所謂「偽書」とよばれている「和田家『文書』」に対して、どこまで踏み込んだ判決が下せるのか…。裁判長の発言と判決に注目と関心が集まりました。(なお、和田氏は欠席。)
注目の判決は、アマチュア歴史研究家が主張した、「『外三郡誌』によって、自分の論文記事の著作権を侵害された」とする主張を退けましたが、一方で、「自分が撮影した写真が和田氏の著書に無断で掲載された」という著作権侵害の主張は認めるという、良い言い方をすれば「玉虫色の判決」、悪い言い方をすれば、「『法曹界特有』の『持って回った言い回し』」の判決内容となりました。これに対し、原告側は控訴の意思を表明し、一方の被告人側代理人弁護士は訴訟の支払金額の少なさを理由に、「実質的には勝訴である」と発言(強弁⁉)するという事態に発展しました。そして、仙台高裁は被告側の主張を一部認めるような判決を下し、最高裁は、「原告側の上告を認めない」という「上告棄却」の決定を下しました。この決定について、原告人側弁護士は「裁判所が『偽書説』に理解を示してくれた」とコメントし、一方で被告人側の弁護士は「真贋論争にこれで『終止符』が打たれた」とコメントするという、「原告、被告側双方が『勝利コメント』を発表する」という異例の事態となったのです。
「偽書」の真贋を訴訟の争点にするのは難しいのか?
では、誰が勝って、誰が負けたのか?ここで法曹関係者のコメントを一部抜粋しようと思います。「現行の法律で、『偽書』であるか否かを訴訟の争点にするには難しいというか、無理なのではないかと思います。というのも、『偽書』であるかどうか、という判断そのものが、法律の問題ではない、と考えられるからです。ただし、原告側の写真の著作権侵害が最高裁で確定したことについては、少なくとも写真の件について、被告側が噓をついていたのが裁判所に認められた、ということになりますから、『原告側の一部勝訴』と言っても問題ないのではないかと思います。」ということだそうです。やはり、「歴史書」の「真贋」については司法の場で争う、というのは難しい(というより無理)のですね。最も、その問題は司法、法務の分野ではなく、あくまでも文科省の守備範囲だ、という本音の声が透けて聞こえますが…。
歴史学者の本音
「わざわざ『ニセモノ』と分かっているものに時間を費やして『検証』するほど
学者は暇人じゃない!」
この問題で有識者からよく言われるのが、「何故多くの『歴史学者』や『歴史学会』は『外三郡誌』や『和田家文書』について、有効な『検証』や『反証』を早期に行わなかったのか」ということです。それが行われていれば、ここまでの被害や影響の拡大は避けられたのではないか、ということです。しかし、筆者としては、この記事を視聴している皆さんにこう問いかけてみようと思います。
「もし、貴方が歴史学者でも、そうでなかった場合でも、『障子紙』に『墨汁』を使って、『筆ペン』で殴り書きした『古文書』と称するものに対して、『興味』と『関心』が示せるか、そのようなものに対して、『研究』のための時間が割けるか、『検証』と『反証』のための『気力』や『モチベーション』を維持できるのか」、ということです。
・和田氏と和田家文書の内容について https://note.com/pe_note/n/nb22be1639fda
つまり殆どの「歴史学者」や「研究者」からしてみれば、「外三郡誌」や「和田家『文書』」などは、「殆ど『ゴミ同然』の代物」で、「『研究』するどころか、『興味』、『関心』を示すだけでも手や筆が汚れる行為」(ある歴史学者)であるということです。こんなものに時間を費やす暇と気力があるならば、自分が研究しているものに回すのが「大人の対応」ということになるのでしょう。筆者もその考えに深く同意します。
和田氏の死去、それでも詭弁を唱え続ける懲りない「擁護派」の面々
その最中に、一連の「和田家『文書』」を「『発見』し続けた」和田喜八郎氏が1999年の9月に73歳で亡くなるという事態になりました。
その後、2000年8月、訴訟の判決によって40万円の慰謝料請求が確定していた和田氏の側が慰謝料請求を拒否し続けたために、原告側が慰謝料の請求の代わりに一連の「和田家『文書』」の「差し押さえ」を実行したのです。原告側は和田氏の実家と「石塔山『荒覇吐』神社」に向かいますが、なんと、どちらにも「和田家『文書』」は一巻も残っていないというまさかの事態に。関係者曰く、「連日『泥棒が』、『トラックで』、『何台も押しかけて』、『全て持って行ってしまった』」とのこと。原告側は苦笑して呆れ返りながら帰らざるを得ませんでした。
では「和田家『文書』」は無くなったのか?と思ったら、「擁護派」のスポンサーの方のもとに「『全巻』、『保管されて残っており』、全部再書をしないといくらになるか分からない」程に膨大であり、 「『今後の』『調査結果次第で』『更なる』『文書の』『発見が』『期待される』」そうです。なお、一連の「和田家『文書』」が「江戸時代」の「寛政年間」に書かれた「原本」を「和田家の『一族』」が「書き写した」「写本」であるため、「「寛政『原本』」が「発見」されれば、更に膨大な量になる」そうです。実際に「擁護派」の巨頭であった古田武彦氏(元昭和薬科大教授、2015年死去)のもとで2007年に「寛政『原本』」なるものが「発表」、「公開」されたものの、「偽書派」の人々の調査の結果、「やはり和田喜八郎氏の筆跡と『完全に一致』していた」(偽史研究家の原田実氏)という代物で、さすがに気まずいと思ったのか、「擁護派」の面々は「東日流外三郡誌(上・下巻)」を「オンデマンド出版」という形での「限定出版」という形で「販売」したのです。しかし、最早このような手法に飛びつくマスコミは存在しなかったようで、「この本はある意味、出版という形をとった自爆テロであるが、それで自爆するのは古田(武彦)氏一人である」(原田氏)という実に手厳しい一言を喰らう結果となったのです。
・古田武彦 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E6%AD%A6%E5%BD%A6
・原田実 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%AE%9F_(%E4%BD%9C%E5%AE%B6)
それでも尽きぬ、終わらぬ「外三郡誌」の「亡霊のような」しぶとさ。
その背景にオカルト、都市伝説ブーム?
このように「偽書派」から「完全に」「フルボッコ」を喰らった「外三郡誌」及び「和田家『文書』」ですが、今もなおしぶとく何かの機会に登場しています。また「擁護派」の面々も全く懲りることもなく、隙あらば「和田家『文書』」は「真書」であるという「主張」を事情を知らない人々にすり込もうと「画策」しているように筆者は感じます。
・擁護派の発言① http://www.torashichi.sakura.ne.jp/yaridamasono43.html
ことに近年は「オカルトブーム」や「都市伝説ブーム」の勢いに乗じて、自らの主張の正当化を図ろうといった意図がありありと感じられます。正直そこまでする「擁護派」の意図は最早筆者の手に余る状況です。
「偽りの『歴史』」無しに東北の「歴史」は語れないほどにつまらない代物なのか?
では、いったい何の情熱があってここまで完膚なきまでに「偽書」の烙印を突きつけられた代物を「正当化」し続けるのか、勿論邪心抜きに「擁護派」の意見を聞けば、「中央政府の歴史書に描かれていない『真実の』『東北の歴史』が書かれている」といった反応が帰ってきますが、筆者の意見としては、「偽りの『歴史』を語らなければならないほどに『東北の歴史』というものはつまらないか?」「『ルサンチマン』(怨念)の吐き散らしに過ぎない『古文書』まがいのモノにすがらなければならないほどに東北の民は卑しい、さもしい存在なのか?」ということです。そのようなものに頼って東北の歴史や文化、伝統を語らなければならないのなら、そんな東北の歴史なんていらない、と思いますし、「東北人」など名乗りたくもない、というのが筆者の偽らざる感想です。
「『古文書』が『大量に』『落ちてきた』」和田氏の家を調べたら…
やっぱり、何も無かった!
2003年の2月に、青森県のブロック紙で、「外三郡誌」を追いかけ続けていた「東奥日報」の斉藤光政記者、偽書研究家の原田実氏、古代史研究家の齋藤隆一氏が当時の和田氏の家の所有者であった和田氏の従妹の和田キヨヱ氏の立会いの下、「和田氏の家」の「現地調査」を実行しました。その結果、そもそも建物が戦時中に新しく建てられたものであること、天井裏に長持ちを吊っておくスペースも、天井の梁に長年縄を縛っていたような形跡も見当たらなかったこと、そもそも梁が細く、「膨大な『古文書』」が入った長持ちを何個も支えられるものではない、ということが分かりました。苦笑するしかない3人に、キヨヱ氏が語りかけました。
「本当に、はんかくさい(青森弁で『おかしい』という意味)話です。私がずっと言い続けてきて来たじゃないですか。『古文書』が落ちてきたという1947年頃、私はこの家に暮らしていたのですが、そんな話も、出来事も一切ありませんでした。そもそも当時は天井板を張っていなかったんですよ。ありもしない『古文書』が、ありもしない『天井板』を『突き破って』『落ちてきた』。しかも、それが『何千巻』もだなんて…。全部、喜八郎さんの作り話です。もともと、この家には何もなかったんです。古い巻物だの、書き物なんて…。そんなものは一切伝わってません。本当にもう、はんかくさい話ですよ。」
・和田キヨヱさんの証言 https://yamataikokunokai.com/katudou/kiroku255.htm
そして一行は、生前に和田氏が「寛政『原本』が家の『中二階』の『壁の中』に隠されている」と「吹聴」していた「中二階」へ。
しかし、誰かに荒らされたのか、中二階の土壁は壊されて、穴が開いていましたが、そこから見えるのは一階の天井裏だけ。また、壁際に大量に置いてあったペットボトルの中には、「新しい和紙を古く偽装して見せるために用意していたのであろう」(原田氏)、「恐らく喜八郎さんの」(キヨヱ氏)尿が。「ここが『偽書』制作の『現場』ということでしょうね」(原田氏)。こうして、「東日流外三郡誌」を含む一連の「和田家『文書』」が、「和田喜八郎さんの手による『偽作』」であるとほぼ完全に証明された形となりました。この事実に対して「擁護派」は未だにくどくどと言い訳がましい反論をしていますが、その声は自分たちの支持者には届くでしょうが、大多数の人々には全くと言っていいほど届いていません。
・和田喜八郎宅の調査結果 https://blog.goo.ne.jp/hi-sann_001/e/b714141229ea991187bc90ae7512d620
「三内丸山遺跡」を筆頭に、東北には誇るべき歴史を伝える史跡が数多く存在する!嘘の歴史なんてオサラバだ!
このようにして、一連の「和田家『文書』」が「偽書」であることは最早疑いようのない事実であることがほぼ証明されましたが、その影響が思ったよりも少なく、小さいもので済んだのは、勿論「偽書派」の人々の膨大な検証結果があったと思いますが、筆者としては、1994年に発掘された、青森の「三内丸山遺跡」をきっかけに、東北の、とりわけ古代からの歴史や史跡が大きく見直され、多くの巷の人々が抱いていた「後進的な地域」というイメージが払しょくされたのではないか、と思っています。さらに近年の「歴史ブーム」も相まって、東北の人々が、「自分達の『郷土の歴史』について引け目を持たなくてもいいんだ」、「誇りを持って語ることがあっていいんだ」という意識の転換が出来たのではないか、とも思っています。
・三内丸山遺跡 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%86%85%E4%B8%B8%E5%B1%B1%E9%81%BA%E8%B7%A1
そうなってしまえば、「外三郡誌」や「和田家『文書』」のような稚拙な「フェイク」などは、もう必要性自体が存在しないものになった、ということが言えると思います。そう、もう東北の人々は、自分たちが生まれ育った地域の歴史を、何も恥ずかしがることなく、堂々と東北や東北以外の方々に語ることが、遅ればせながらではありますが、ようやく出来るようになったということです。そしてそのことは、未来の東北をきっと明るくする事が出来るきっかけになれる、と思います。
まとめ
今回は「東日流外三郡誌」についてご紹介しました。「東日流外三郡誌」については青森以外では知名度は薄いですが、東北地方の遺跡や、公的機関や様々なイベントにその影響が未だに残っており、筆者自身が「何とか、どうにかしなければ」という思いで、今回執筆いたしました。
今後もこのような、東北の歴史などについてのコラムを書いていこうと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
それではまた次のコラムでお会いしましょう!ライナスでした!
