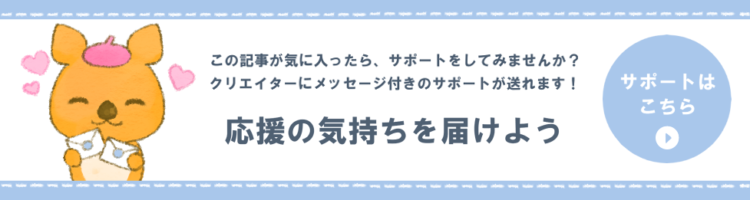震災から三日後の夕方、私は朝からハイダルさんの友人が関東から駆けつけて食料をハ イダルさんのカレー屋に運ぶのを手伝った。ハイダルさんの友人は、初対面の私に笑顔で 接してくれて、感じの良い印象を受けた。そして、私はインド人のシェフと一緒に甘口のラムカレーを作るのを手伝うのであった。 私は今まで、本格的なカレーを作った事はなかった。家では、レトルトカレーかカレーのルーを溶かして使うタイプのカレーしか作った事はない。本格的なスパイスを使う事も なければ、微妙なさじ加減で辛さを出す事もない。いわゆる日本人向けのカレーしか知らないのだが、ここのカレー屋さんで、本格的なカレーの作り方を知ったのであった。
私は、震災の前の月、二月からの付き合いで、まだ付き合いは短かったが、なぜかパキ スタン人の人達に親近感を抱くのであった。それは彼らが日本語を流暢に話せるという訳 でもなく、カレーをご馳走してくれるからでもなかった。その親近感は、なんなのかと考えるのであった。
震災から、四日後のお昼だった。この日は、いつも通り震災で被災し食べ物に困っている人達が大勢きた。この日は、百五十食以上準備していたので大勢の人達にカレーを提供 できる事ができるとハイダルさんはじめハイダルさんの友人も意気込んでいた。もちろん、 カレー屋の外国人の店員たちも。そして、私もみんなの影響からか、カレーを提供する事が嬉しくなってきた。それは、ただの興味本位のボランティア精神ではなく、本当に困っている人を助ける人の営みのように感じた。
夕方になり、外はもう暗くなっていた。私は、ハイダルさんの関東から来てくれた友人と別れの挨拶をした。また、食料を送ってくれるとハイダルさんと約束しているのを見かけた。恐らく、また来るのだろう。私もその日は帰る支度をして、自宅に帰ろうと身支度をしていた。
その時だった。インド人のシェフが、余ったカレーをタッパーに入れてくれた。私はそれを受け取り感謝の言葉を言った。ハイダルさんにも挨拶しようとハイダルさんに声をかけた。
「ハイダルさん、今日はお疲れ様でした。カレーもありがとう。インド人のシェフから貰 ったよ」
「先生、お疲れ様です。カレー美味しく食べてね。カレー屋の手伝いもありがとう」
私は、ハイダルさんのその返事を聞いて思う事があった。ハイダルさんは私の事を先生 と言うが、私は実際には先生と呼ばれる程、大した事はしていないという事だ。ハイダルさんが愛着を持って先生と呼んでくれるのは嬉しく思っていたが、私が付き合ってきた短い時間の中で、私はハイダルさんこそ先生という称号にふさわしいのではないかと心から感じるものがあった。そして、私は言った。
「ハイダルさんは私の先生ですね。いつも、私の事を先生と言うけどハイダルさんこそ先 生だよ。これからもよろしくね、ハイダル先生」
私がそう言うと、ハイダルさんが言った。
「私は先生じゃないね、良い先生ね」
ハイダルさんが、私と初めて会った時のような冗談を言って、二人で笑いあった。 雪が降る空の下、私とハイダルさんは帰り際に、強い握手を交わした。手は冷たかった が、握手を交わした時間は長く、熱のこもった握手だったので、手に降りかかる雪は解けていった。
おわり