「噓をまとめたジョンカラ節」か!?
青森・「東日流外三郡誌」(つがるそとさんぐんし)
を検証する
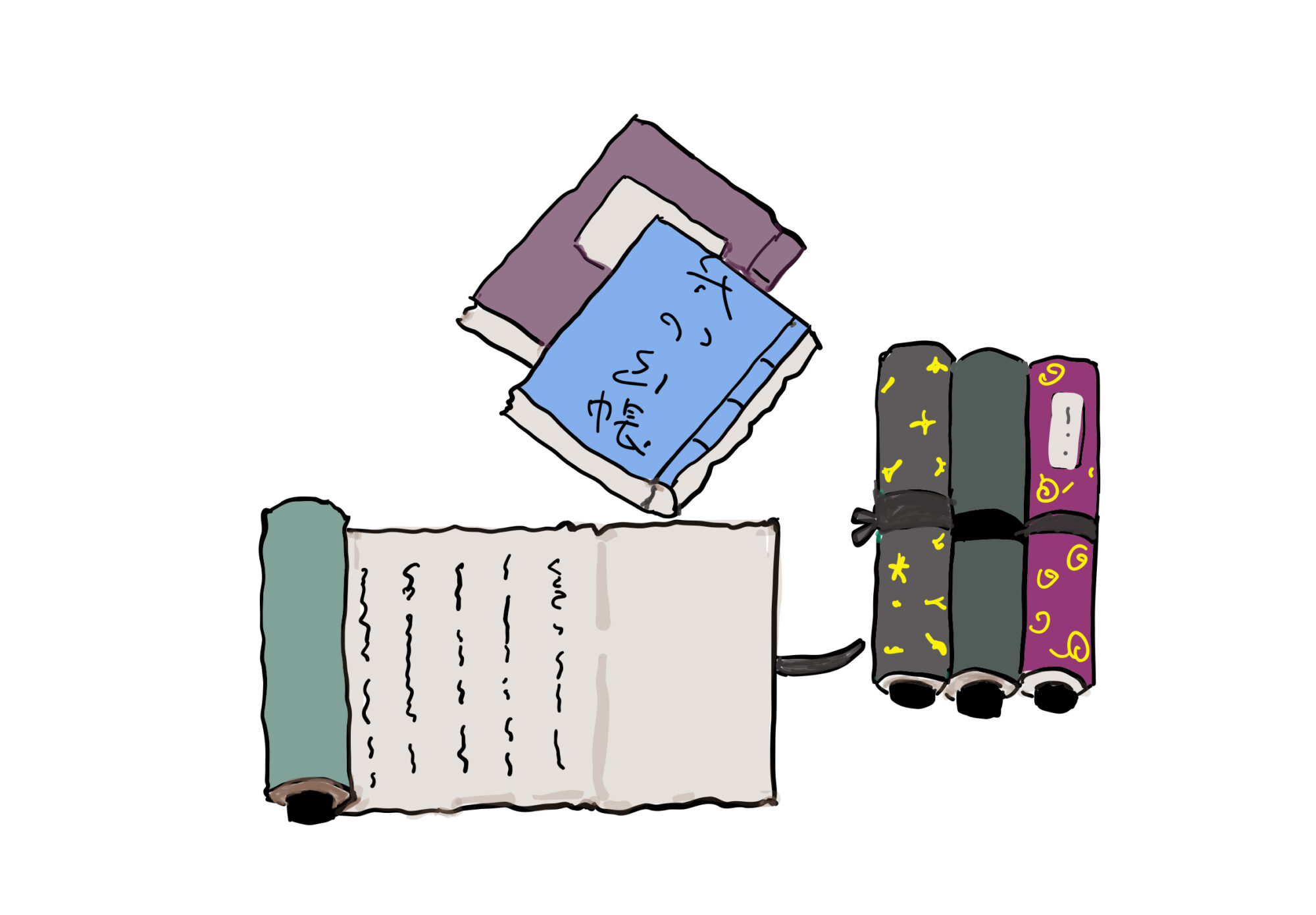
ライナス
皆さんこんにちは。ライナスです。今回は、一部の歴史愛好家の間で話題と真贋論争を呼び起こした、青森県の歴史書「東日流外三郡誌」について、筆者なりの検証をしてみようと思います。どうぞ最後までご覧ください。
「『家の天井の屋根裏から』長持に収められた『大量の古文書』が『落ちてきた。』」そこから話は始まった。
「『つがるそとさんぐんし』って何⁉初めて聞いた!」という皆様のために、まず最初から説明しようと思います。事の始めは1948年に、青森県の五所川原市飯詰村(現在の五所川原市)の「炭焼き職人」の和田喜八郎(わだきはちろう)氏が「自宅の『改装中に』『天井の屋根裏から』長持に収められた『大量の』『古文書』が『落ちてきた』」と言う触れ込みで伝えられました(今回はかなり「」と『』を使う文章が多くなることを、予めお伝えしておきます。ご了承ください。)。その後も「古文書」が「発見され続けて」、一躍和田氏は青森で有名人となります。その後公的機関が和田氏の「和田氏の『古文書』を町や村の歴史資料として編纂して『町おこし』の材料にしたい」という事から1973年に編纂された西津軽郡の車力村(しゃりきむら)の「車力村史」を皮切りに、1975年に北津軽郡の市浦村(しうらむら)から「市浦村史資料編」として公的機関から刊行されて、「『公的機関』の『お墨付き』を得た『歴史資料』」とみなされました。その後も「続々と」「発見される」「『古文書』や『資料郡』」から一連の「文書」は「和田家『文書』」(わだけもんじょ)と呼ばれるようになりました。
・車力村 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E5%8A%9B%E6%9D%91
・市浦村 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E6%B5%A6%E6%9D%91
「古代の東北地方に大和朝廷とは違う『東北独自の王権・王朝』が存在した」という触れ込みの「古文書」
さて、そういった経緯で世に発表された「東日流外三郡誌」ですが、内容はどのようになっているのでしょうか?それを説明したいと思います(もし内容を見て「そんなの在り得ない!」と思われた方は、読み飛ばしてもらっても構いません。)。
「東日流外三郡誌」は、江戸時代後期に三春藩(みはるはん。現在の福島県田村郡三春町)を治めていた秋田氏(あきたし)の藩主の秋田千季(あきたよしすえ「倩季」とも書く。)の「密命を受けて」、その「縁者」の「秋田孝季」(あきたたかすえ)とその「妹婿で」、現在の青森県五所川原市の「石塔山『荒覇吐』神社」(せきとうさんあらはばきじんじゃ)の「『神官』を『務めていた』」、「和田長三郎吉次」(わだちょうざぶろうよしつぐ、「外三郡誌」の中では「発見者」の和田喜八郎氏の「直接の先祖」と描かれている)の2人が、「『全国』や『海外』を」「調査」して、かつて秋田を治めていた頃の秋田氏が「安東氏」(あんどうし)を名乗っていた時代の歴史の足跡をたどりながら、かつての古代東北地方の「王朝」の実態を解明していくという「体裁」を取っています。
・三春藩 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%98%A5%E8%97%A9
・安東氏 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F
・秋田氏 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%B0%8F
・秋田千季(倩季) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E5%80%A9%E5%AD%A3
先ず、古代の津軽地方には、「阿曽辺族」(あそべぞく)という「文化程度の低い」「温厚な未開部族」が「先住民」として住んでいたそうで、その「阿曽辺族」が岩木山(いわきさん)の噴火によってほぼ全滅しかけたところに、中国のツングース系の「好戦的」で「残虐」な「津保化族」(つぼけぞく)という「部族」が「大陸から流れ込み」、「阿曽辺族」を「虐殺し」、「津軽を平定」したところに、古代中国の「晋の献公」(しんのけんこう)に追われた「郡公司の『一族』」(ぐんこうしのいちぞく)と、神武天皇(じんむてんのう)に追われた「邪馬台国の『一族』」(やまたいこくのいちぞく)が「津軽に流れ込み」、「津保化族」を「平定して」、やがて「諸民族」が「混血」して「荒羽吐族」(あらはばきぞく)を「名乗るようになり」、やがて「荒覇吐『王国』」(あらはばきおうこく)を建国し、「荒羽吐の『5王』(あらはばきのごおう)」を「制定」して、古代の東北地方を「統治」していたそうです。
・献公 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%AE%E5%85%AC_(%E6%99%8B)
しかし、神武天皇の「大和朝廷」側はこれを良しとせず、彼らを「蝦夷」(えみし)と呼ぶようになったそうです(なお、「外三郡誌」の中では、この「荒羽吐の『5王』」こそが中国の歴史書に出てくる「倭の五王」だとされています。)。そして「外三郡誌」の中では「邪馬台国」から「津軽に」「落ち延びてきた」安日彦(あびひこ)と長髄彦(ながすねひこ)の子孫が安倍氏、安東氏を経て秋田氏につながっていると「記載」されています。
・神武天皇 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%AD%A6%E5%A4%A9%E7%9A%87
・倭の五王 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E3%81%AE%E4%BA%94%E7%8E%8B
・長髄彦 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%AB%84%E5%BD%A6
このように、「外三郡誌」には「日本書紀」などには書かれない、「古代」の「津軽」と「東北地方」の「歴史」が「書かれて」います。そしてそのこと自体が、これまでに常に中央政府に圧政され続けてきた東北人の心の琴線に触れただけでなく、「真実の東北の歴史を知りたい」という東北以外の一部の歴史愛好家や読書ファンなどに支持され、その勢いで町や村から「地域おこし」の一環として「外三郡誌」や「和田家文書」を「町や村の資料として刊行したい」という地域自治体の後押しを受けて、「車力村史」や「市浦村村史 資料編」という形で刊行されることとなったのです。
早期から出ていた「偽書説」、
アマチュア歴史研究家からの訴訟で
一気に「偽書」に雰囲気が変わる
このように当初は順調な評価を受けていた「外三郡誌」でしたが、青森県の古文書研究会が「偽書」説を唱えたのを皮切りに、当時の産業能率大学教授の安本美典(やすもとびてん)氏が「和田喜八郎氏の筆跡の『誤字、癖字』と『外三郡誌』や『和田家文書』との筆跡の『誤字、癖字』が完全に一致している」として、「『外三郡誌』や『和田家文書』は江戸時代に描かれたものではなく、恐らく昭和から『発見者の』和田喜八郎氏によって描かれた可能性が非常に高い」という結果を発表していました。しかし、周辺からの反応は鈍く、また「和田家『文書』」が車力村や市浦村の「公的機関」から発刊されていたことも相まって、「偽書説」はあまり世間一般的に受け入れられることはありませんでした。しかし、大分県在住のアマチュア歴史研究家の方から、「自分が調査・研究している近畿地方の石垣の写真を無断で和田さんの『著書や古文書』に『盗用』された」という訴訟が起こったのを機に、これまでに様々なメディア媒体で、「和田家『文書』は『偽書』である」と発表してきた「偽書派」の人々が一致結束して、一連の「和田家『文書』」に対して、大々的な反証を行い始めたのです。
・安本美典 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E5%85%B8
「古文書」の内容も、
和田喜八郎氏の経歴も、
全部デタラメ、ウソだらけ!
こうして大々的な反証を行い始めた「偽書派」の人たちですが、その内容が想像を絶するほどに細部を極めたものでした。全部を描くと膨大な分量になるので、ここでは主要なものを抜粋しようと思います。
「和田家『文書』」について
・「秋田孝季」と「和田吉次」の実在及び存在が「和田家『文書』」意外に確認できない。
・「和田家『文書』」に使われた紙を検査してみた結果、戦後の所謂「障子紙」であることが分かった。
・「和田家『文書』」に使われた墨は戦後に量産された「墨汁」であった。(「墨汁」は江戸時代には存在しない。)
・「和田家『文書』」に使われた筆記用具は当時使われていた竹筆や毛筆ではなく、現代の所謂「筆ペン」だった。
・「和田家『文書』」に描かれた多くの挿絵(さしえ)が、戦時中に発刊された「國史画帖大和櫻」(こくしがちょうやまとざくら)からの「盗用」であった。
・國史画帖大和櫻 https://www.youtube.com/watch?v=feLKQwQoUyc
・「キリストの『墓』が青森にある」「『ムー大陸』が存在した」など戦後に吹聴された話が散見される。
・「秋田孝季」と「和田吉次」は長崎に菅江真澄(すがえますみ)とともに赴き、オランダ人宣教師から「進化論」や「ビックバン」、「大陸移動説」などを学んだとされているが、禁教令の幕府政権下で宣教師がいるはずがなく、またいずれの説も発表された当初と「文書」との年代が符合せず、また当時のキリスト教世界では「異端」とされていた説で、改宗していない日本人に教える理由がない。また、菅江真澄が長崎に赴いた記録が存在せず、菅江の著書に「秋田孝季」や「和田吉次」の名前がない。
・菅江真澄 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E6%B1%9F%E7%9C%9F%E6%BE%84
・「秋田孝季」と「和田吉次」がロシア、中国、朝鮮半島、ヨーロッパまで渡ったとされているが、当時の鎖国政策の状態で渡海できるわけがない。
・「和田家『文書』」には戦後、しかもごく最近使われるようになった「言葉」や「知識」が散見される。
和田喜八郎氏の経歴について
・和田喜八郎氏は「先祖は「石塔山『荒覇吐』神社」の『神官』だった」と吹聴しているが、「和田家『文書』」以外にその記録がない。
(なお、和田の親類、知人によれば、和田の先祖は代々農家の出身で、「神官」をしていた事実は存在しない。また、「石塔山『荒覇吐』神社(大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)とも呼ばれる)」についても、和田氏が自身の発言の体裁を整えるために地元の水神様の祠を「改修」したものであり、ご神体の仏像も中国の古物商店から安価で購入したものだった。)
・石塔山荒覇吐神社(大山祇神社)https://www.bonjyu-furesen.info/wp-content/themes/original/img/magazine/etc01.pdf
・和田喜八郎氏は静岡県天竜市二俣町の「通信研究所」で学んだと書いているが、そのような事実はない。
・「陸軍中野学校」に入隊していたとされているが、関係者から「和田という人物が入隊した事実はない」とのこと。
・陸軍中野学校https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%AD%A6%E6%A0%A1
(なお、和田氏の年齢、学歴を考えても、中野学校への入隊は事実上不可能である。)
・「陸軍から海軍に『転籍』した」と語っているが、当時の日本軍の制度上そのような事は出来ない。
・ミャンマー(当時はビルマ)の「マンダレーで『敗戦の報を聞いた』」「モンテンルパで三年間収容された」と語っているが、陸軍は敗戦前にマンダレーから撤退しており、敗戦の報を聞く事は出来ない。また、フィリピンのモンテンルパ収容所に収容されたという事実も、GHQおよび連合国の記録にはない。
(後に和田氏の親戚や知人が証言しているが、和田氏が戦前及び戦時中に郷里から出ていた事実自体がない。)
・「元皇宮護衛官」を自称し、青森県の警友会に所属していたが、宮内庁から「事実無根である」と言われている。青森県警友会からはその後除名された。(和田本人は後に「『ボランティア』として皇宮を警備していた」と吹聴している。)
・皇宮護衛官 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%AE%E8%AD%B7%E8%A1%9B%E5%AE%98
などなど…。「外三郡誌」を含めた一連の「和田家『文書』」がウソとデタラメのオンパレードなら、和田喜八郎氏の経歴もまた然りという、まさに「トンデモ」状態。「偽書派」の識者からは一連の「和田家『文書』」を「五流の偽書」(郷土史家・山上笙介)、「ウソをまとめたジョンカラ節」(青森ペンクラブ会長・三上強二)といった厳しい言葉が飛び交う事態となりました。
