始まりは「塩漬け肉」
昨今、筆者はダイエットと食費節減の為に、職場では自分で作ったケークサレを昼食にし、自宅での昼食になるときには、お米とオートミールで作ったお粥とハム、もやしという食生活を送っております。
毎回ハムを食しておりますが、しばらく食していると歴史が気になるようになり、調べてみる事に致しました。
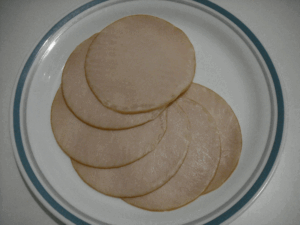
スライスしたハムの画像
もともとは、狩猟採集生活が行われていた時代に、狩猟で得た動物の肉を塩漬けにしていたのが、ハムやベーコンなどの加工食品の始まりだそうです。
そして、7000年ほど前に豚が家畜化され、楔形文字の時代の古代バビロニア王国や、中国でもそういう系統の豚肉加工食品が作られていたと書いてありました。
日本で今食されている欧州産のハムは、12世紀から13世紀頃に、作り方が確立したものです。
スパイスやハーブが使われるようになって発展
その前までは、生ハムのようなものが主流だったのですが、十字軍遠征によってスパイスやハーブが欧州に入荷され、味付けされたハムやベーコンができました。
ちなみに、ハムとベーコンの違いは、もも肉で作られたものがハム、バラ肉で作られたものがベーコン、という事になっております。
ざっくりと作り方を見ると、肉から血を抜き、塩や香辛料で味付けして、燻製にする、という過程を経てハムになります。
よくスーパーなどの店頭に並んでいて、私の昼食のメニューである「プレスハム」は、いろいろな部位の豚肉や牛肉などを塊に仕立ててから味付けや燻製を施したものということがわかりました。
生ハムはかなり高価なのに、プレスハムは比較にならない程安価なのは、豚のモモ1本を日時をかけて熟成させるのが生ハムなのに対し、豚以外の肉も使った塊を味付けしてざっくりと燻製にして短期間で材料費もかからないからのようです。
やはり、時間と手間と材料にこだわると、値段が上がってしまうものです。
とはいえ、生ハムなら全部おいしいかというとそんなこともなく、昔、あるお店でいただいた有名なイベリコ豚の生ハムは保存方法が悪かったようで、少しカビ系の味がしたのを思い出します。
日本でのハム文化はこれから
日本では肉食の歴史が浅く、まだまだ洗練されているとは言い難いハムやベーコンの食文化ですが、昨今、独自の生ハムやおいしい鶏のハムなども作られてきているのは、心強く思います。或る生産者様は、ハンガリーの「食べる国宝」と呼ばれるマンガリッツァ豚を輸入して育て、日本産のおいしい生ハムを作る、という遠大な計画を立てておられるようです。うまくいって、日本人好みのおいしいハムができることを期待しております。
ハムの歴史
